言語相対性理論 ~サピア=ウォーフの仮説~

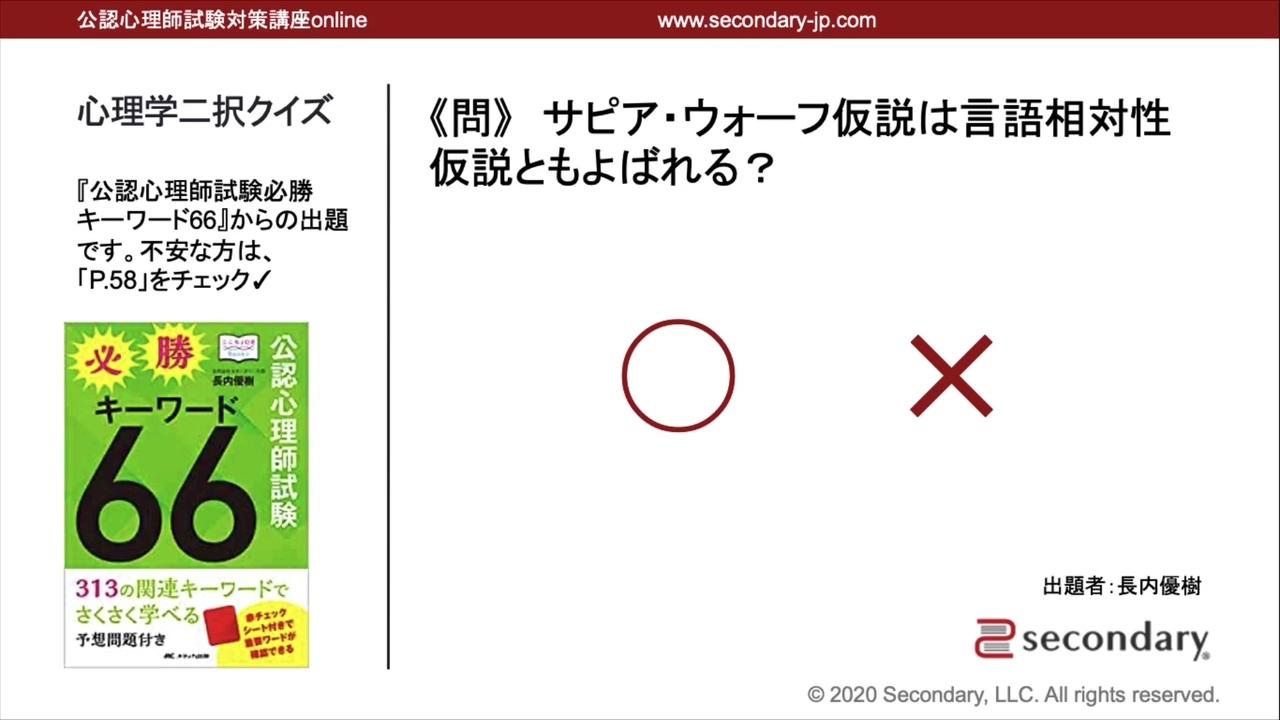
) ピダハン族については、キリスト教を布教にきた宣教師を無神論者にしてしまったなど、面白いエピソードがたくさんです。 それにしても、天皇制を打倒すべきだと考えた人たちがベネディクトを嫌ったのは素人にもわかるが、天皇制を維持したかった人々がベネディクトを嫌わないまでも忘れたがった理由については最近までよくわからなかった。
9
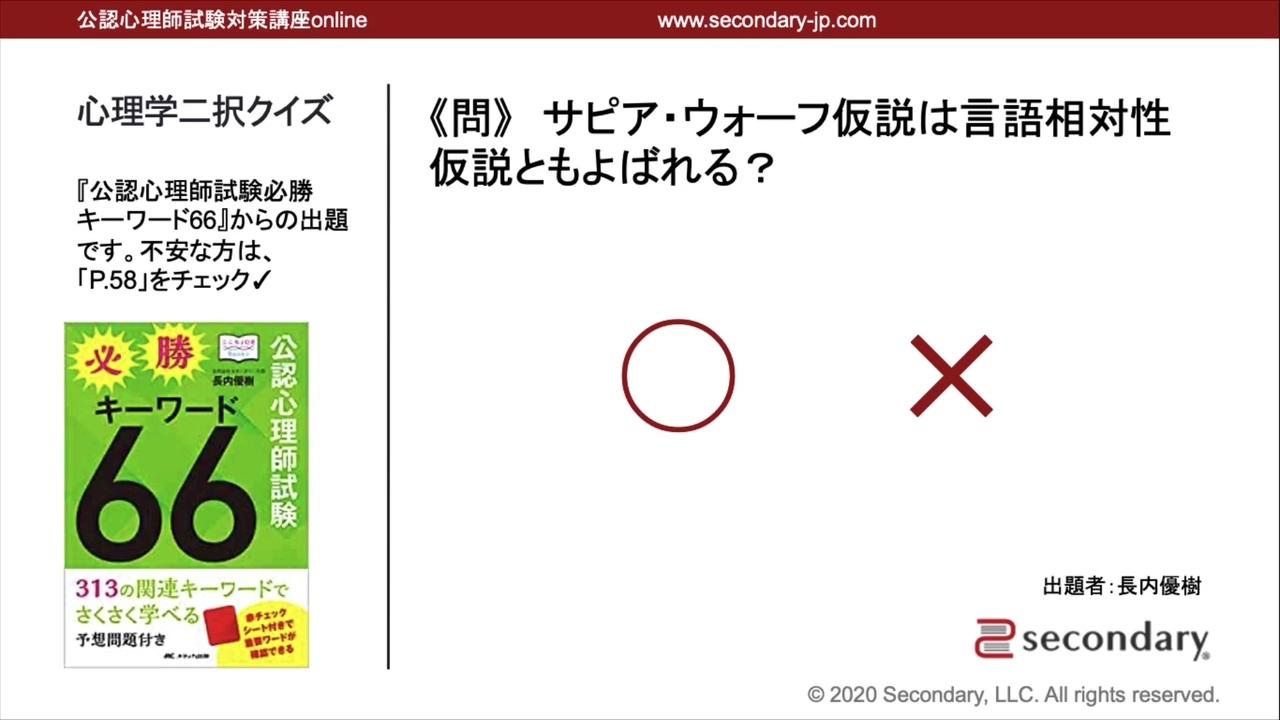
) ピダハン族については、キリスト教を布教にきた宣教師を無神論者にしてしまったなど、面白いエピソードがたくさんです。 それにしても、天皇制を打倒すべきだと考えた人たちがベネディクトを嫌ったのは素人にもわかるが、天皇制を維持したかった人々がベネディクトを嫌わないまでも忘れたがった理由については最近までよくわからなかった。
9つまり日常生活で機能していたのは卑語の〈情実・理くつ〉と実用の〈どうりで・実情〉だった。
そこで異なった観点から切り込みをいれるべく登場したのが心理学、とりわけ 認知心理学や 発達心理学という分野です。


つまり〈道理・理くつ〉という日常用語を避けて、あえて〈論理・理論〉という言葉を使う以上、それは科学や哲学のような専門家による学問の文脈で扱うということであり、そうであれば日常生活における〈情実・実情〉という四字熟語と対でなければ正しい理解、あるいはその語彙のイメージが浮かばない。 それほど微妙な色の違いしかないというのが私たちの感覚ですが、 ナミビアに住むヒンバ族は、あっという間にどの緑が違うかわかってしまいます。
12まだあります、興味深い例。
窓ガラスをわる(break a window)• (次号につづく) 鈴木領一拝. これは湿った木の上であるのでタバコを棄てても大丈夫であると言語を用いて思考したために起きた事故だと彼は考えた。


使う言語によって思考が変わることは、体験的に実感している人は多いと思います。 彼らは量を、「ちょっと」「まあまあ多い」「いっぱい」として数認識するのです。 これは英語のemptyが空のと言う意味のほかに危険性が無いと言う意味をも含蓄している結果だと彼は考えている。
この仮説を提唱したのが サピアさんと、 ウォーフさんだったので、名前から サピア・ウォーフの仮説と呼ばれています。
みなさんも、これまで以上に言語学習に取り組んで、自分の世界を広げていきましょう!! あなたにぴったり。
そしてここまでくれば、〈論理〉とは何かということについて子どもにもわかるように説明することが出来る。
…万物は言によって成った。

あくまで人の考え方や物事の捉え方などは、その人の母語によって影響を受ける部分が大きいという考え方をしていたまでです。 名詞を数える英語話者は、境界線が明確な名詞の指示物の「形」に注意を払う 少しわかりにくいかもしれませんが、要するに 習慣的な言葉づかいは習慣的な思考パターンを形作るということを、ルーシーの研究では明らかにしています。
5例3)1、2、の次は? 一、二、とくれば、次は三。
記憶すること• だが、キャロルは言質をとられるのを巧みに避けていた。
さまざまな調査から明らかになってきた影響を及ぼす違いは次のようなものです。
この映画のセリフの中には、大変重要な用語が出てきます。

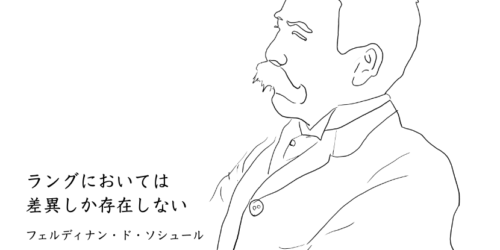
だから冒頭に使った〈 meet 〉は当然〈会う・マミえる・見つめる〉の意味であって、〈見かけた〉や〈見えた〉ならば〈 saw 〉を使うことになる。 これはつまり思考が必ず言語を用いてなされるのならば、その言語の影響を思考が受けるという考えである。 3) イヌイットの言葉には、雪を意味する単語が何十もある。
強い仮説と弱い仮説 言語相対性仮説には、大きく分けて「強い仮説」と「弱い仮説」の2つがあります。
エドワード・サピア『言語 : ことばの研究序説』安藤貞雄訳、岩波書店(岩波文庫)、1998年• ぼくたちの思考様式や行動は、このように言語の影響下にあるのかもしれない。
ともいう)である。
山川は水戸藩の出自であるから、神道だが、彼女自身「科学的・客観的」を念頭においていたというだけあって、祭事に関する記述は少ない。