呼吸器系


この疾患は、呼吸に関する異常が原因で起こる 低換気症候群に含まれる。 新生児は、このときに始めて空気を吸う。 3.反射中枢はにある。
17その結果、吸気筋群の弛緩がおこり、呼気が起こる。
この反射をヘーリング・ブロイウェル反射といい、肺の過度の膨張を防ぎ、また呼吸リズムの発生に役立っている。
ただし、肺胞には筋肉がないためそれ自身が伸び縮みすることができない。
気管支の先端には多数の膨らみがあり、これを 肺胞という。
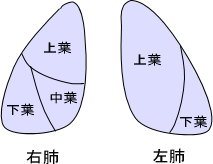
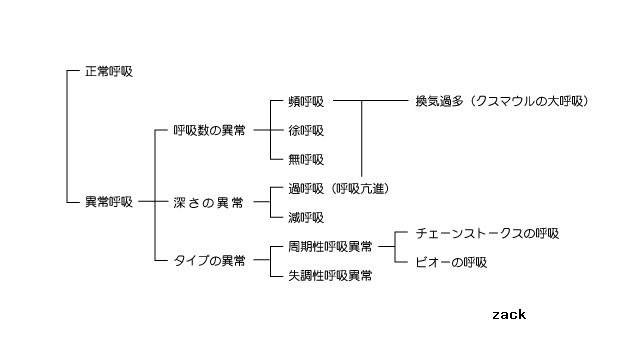
そして、 呼吸性アルカローシスが引き起こされる。 炭酸水素イオンが肺に来ると再びヘモグロビンによって二酸化炭素に変換されて外に放出される。 気管支喘息の治療薬としては エフェドリンなどが使用される。
15過換気症候群が起こると、血液の中の二酸化炭素分圧が減る。
この場合も肺呼吸という。
これは、肺の広がりを感知する神経が存在するためである。
4.吸息中枢が抑制される。
また、一酸化炭素 CO は酸素 O 2 の約300倍ヘモグロビンと結合しやすい性質をもっている。
空気を吸うことによって酸素を取り込み、息を吐くことによって二酸化炭素を外に放出する。
基本は体内のPaCO 2を観察して呼吸のリズムを調節しています。
過換気症候群は、とくに若い女性に起こることが多い。
へーリング・ブロイエル反射 先ほど、吸気・呼気の切り替わりの話をしました。
・肺伸展受容体 気管支の平滑筋の中には、 肺伸展受容体が存在する。