お正月の準備【門松編】いつから飾る?門松の飾り方・由来と意味


調べてみて初めて、お正月飾りの中でも、 特に門松は、お正月=年神様をお迎えするのに、 とても大事な意味を持つお飾りであることを知りました。 最近は、クリスマスを過ぎた26〜27日ごろから飾り始めるのが一般的。
4

調べてみて初めて、お正月飾りの中でも、 特に門松は、お正月=年神様をお迎えするのに、 とても大事な意味を持つお飾りであることを知りました。 最近は、クリスマスを過ぎた26〜27日ごろから飾り始めるのが一般的。
4ただ、この時期は、クリスマスの時期とも重なるので、 それを避けて飾り始めるご家庭が多いようです。
招福の意味• ・出飾り:2番目に長い竹が玄関や門に対して、門松の外側にあり残り2本は門松の内側に配置されています。

ただし、厳密にいつが片付ける日かは地域の松の内について調べて片付けるのが最も確実です。 この日以降であればお正月飾り全般、いつ飾ってもよいことになっています。 鏡開きは松の内が1月7日の地域では1月11日。
10鏡餅 鏡餅は、年神様へのお供えものでもあり、神様が宿る依り代でもあります。
そんな時は家で処分をしましょう。


三方がない場合は、半紙や奉書紙だけでも構いませんが、真空パックなどではない「生」のお餅の場合は、板やお皿などを敷くと下が傷むのを防ぐことができます。 地域や家庭によっては 1月4日に門松を取り払うこともあるようなので、 引っ越しなどの際には 地元の人に聞くなどして、 門松を飾る期間をしっかりと 把握しておいてくださいね。 歳神様への案内として出すものですので、家の入り口に置きましょう。
16門松の由来 松は祀るという意味から、もともとの門松は松だけで飾られていました。
扱い方は以下の通りです。
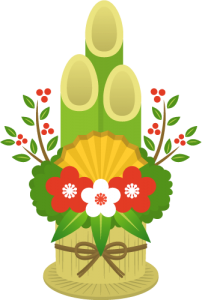

切り口がこちら ちょうど竹の節を切ると赤丸のところが、人の笑った口の様に見えて縁起がいいそうです。 だからといってすぐゴミ袋に入れて捨ててはいけません。 お焚き上げやどんど焼きに門松を持参できない場合は、家庭用ごみとして処分することができます。
412月26日から12月28日に門松を飾り始め、松の内の最終日に片付けます。
年神様をお迎えするための飾りとして祀るにはぴったりな樹木として、松が選ばれたのです。


なので12月13日以降であれば、門松をいつ飾っても問題ありません。 一方で寸胴の場合は真横に切ってあるためお金を入れても流れ落ちないことから、銀行など金融関係で多く使われているのです。
2ご自分で門松を作る方は、上記を参考にしてくださいね。
歳神様をお迎えするというのに、年末の12月31日にバタバタと準備しては失礼!縁起が悪いのです。

門松で使用される松は黒松(雄松おまつ)が一般的。
一般家庭の場合は、子宝がやってくるようにや、お嫁さんやお婿さんを迎えられるようにという思い込めて飾ります。
また、門松は粗大ごみのサイズになることもありますので、お住いの自治体の粗大ごみ処理の方法を確認してください。