源氏物語「須磨の絵日記」
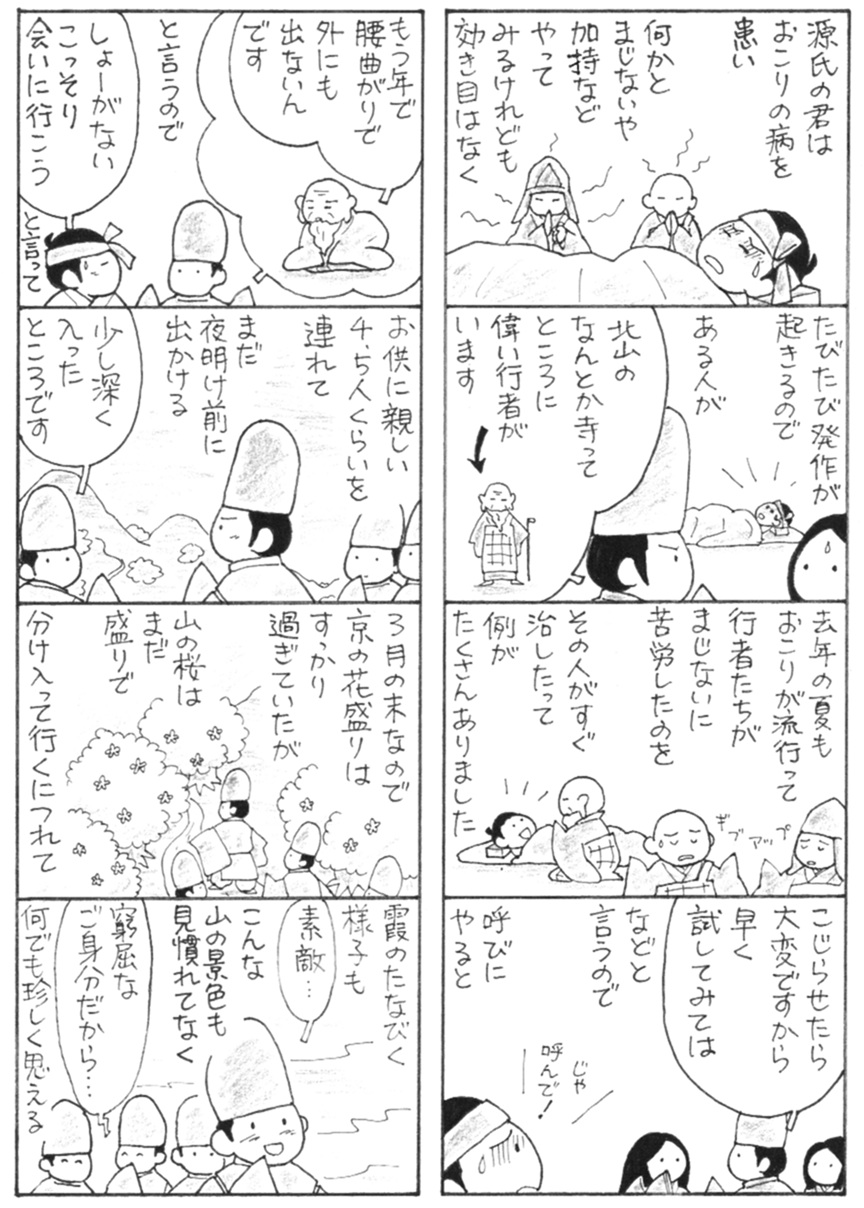
」と言う。 親の常陸 ひたちになりて下りしにも誘はれで、参れるなりけり。
13軽々しき名・・・軽率だという評判。
動作の対象である光源氏を敬っている。


(私には)珍しく思われましたよ。
つまらないことで(私が)他人から悪く思われまいと思うのも、ただあなたひとりを思うためなのですよ。
おん夢の中にも、(前に見たのと)全く同じ様子をしたものばかり現われて来ては、(源氏に)つきまとい申す、とご覧になる。
(でも)ほんとにこうも地の底に通るほどの雹が降り、雷のやまないことは(都では)ございませんでした。 (源氏の君の)おそばには、お付きの人もたいそう少なくて、(それも)みな寝ているのに、(源氏は)ひとり目をさまして、枕から頭を上げて、あたりの嵐を聞いていらっしゃると、波がすぐ枕もとにうち寄せてくる気がして、涙がこぼれ落ちるとも思われないのに、(涙で)枕が浮くほどになってしまった。
(帝からいただいた)おん衣は、(詩のとおり)ほんとうに身から離さないで、そばにお置きになっている。
今回は源氏物語でも有名な、「須磨の秋」についてご紹介しました。
る=完了の助動詞「り」の連体形、接続はサ変なら未然形・四段なら已然形。
光源氏 初雁 はつかりは恋しき人の列 つらなれや旅の空飛ぶ声の悲しき 初雁は都にいる恋しい人の仲間なのだろうか、旅の空を飛ぶ声が悲しく聞こえてくるよ。
正気の者はみな。
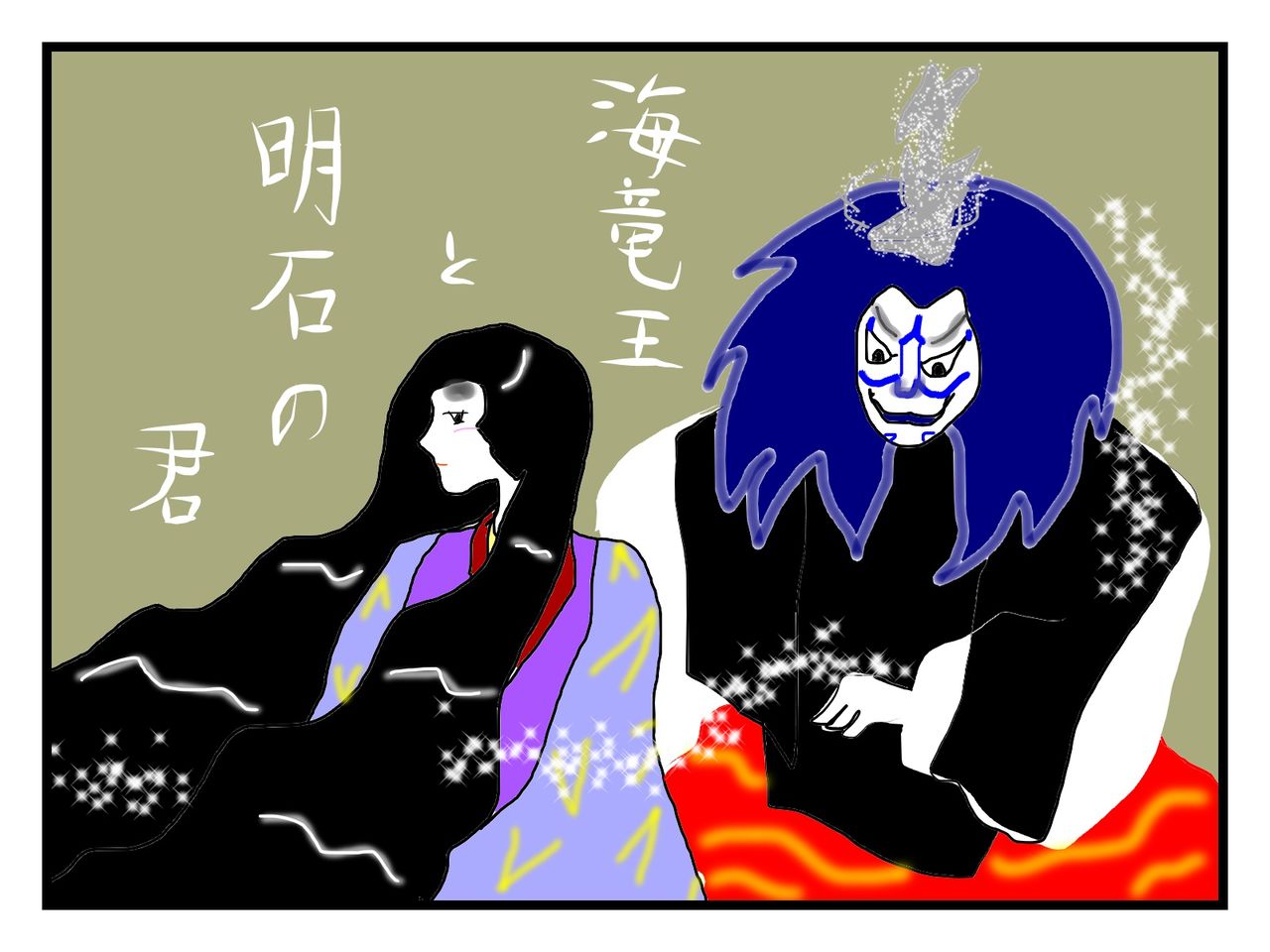

(そうは思いますが)命はどうも思い通りになりにくいもののようです。 明瞭に。
良清・・・播磨の守の子で源氏の家来。
」とおぼせば、昼は何くれとたはぶれごとうちのたまひ紛らはし、つれづれなるままに、いろいろの紙を継ぎつつ手習ひをし給ひ、めづらしきさまなる唐の綾などにさまざまの絵どもを書きすさび給へる、屏風のおもてどもなど、いとめでたく、見どころあり。

こまやかなる御直衣 ここは濃い縹 はなだ色の御直衣。 とのたまへば、 良清 よしきよ 、 とおっしゃると、良清が、 かきつらね 昔のことぞ 思ほゆる 雁はその世の 友ならねども 次から次へと昔のことが思い出される。 (源氏の)御前にはほんとうに人少なで、みな寝静まっているのに、(源氏は)一人目を覚まして、枕から頭をもたげて四方の激しい風を聞いていらっしゃると、波がここまで寄せてくる気がして、涙が落ちるとも気づかないうちに、枕が浮くほどになってしまった。
12」と(供人が)申し上げるけれど、やはり奥にお入りにならない。
げに(実に)=副詞、なるほど、実に、まことに。
現代語訳 須磨では、ひとしお物思いの限りを尽くす秋風によって、 海は少し遠いけれど、行平の中納言が、 「関吹き越ゆる」と詠んだという浦波が、 毎夜はなるほどとても近く聞こえて、 この上なくしみじみとした趣があるものは、 こういう所の秋であったよ。
もの寂しい、おそろしい、恐ろしいぐらい優れている 聞こゆれ=ヤ行下二段動詞「聞こゆ」の已然形。
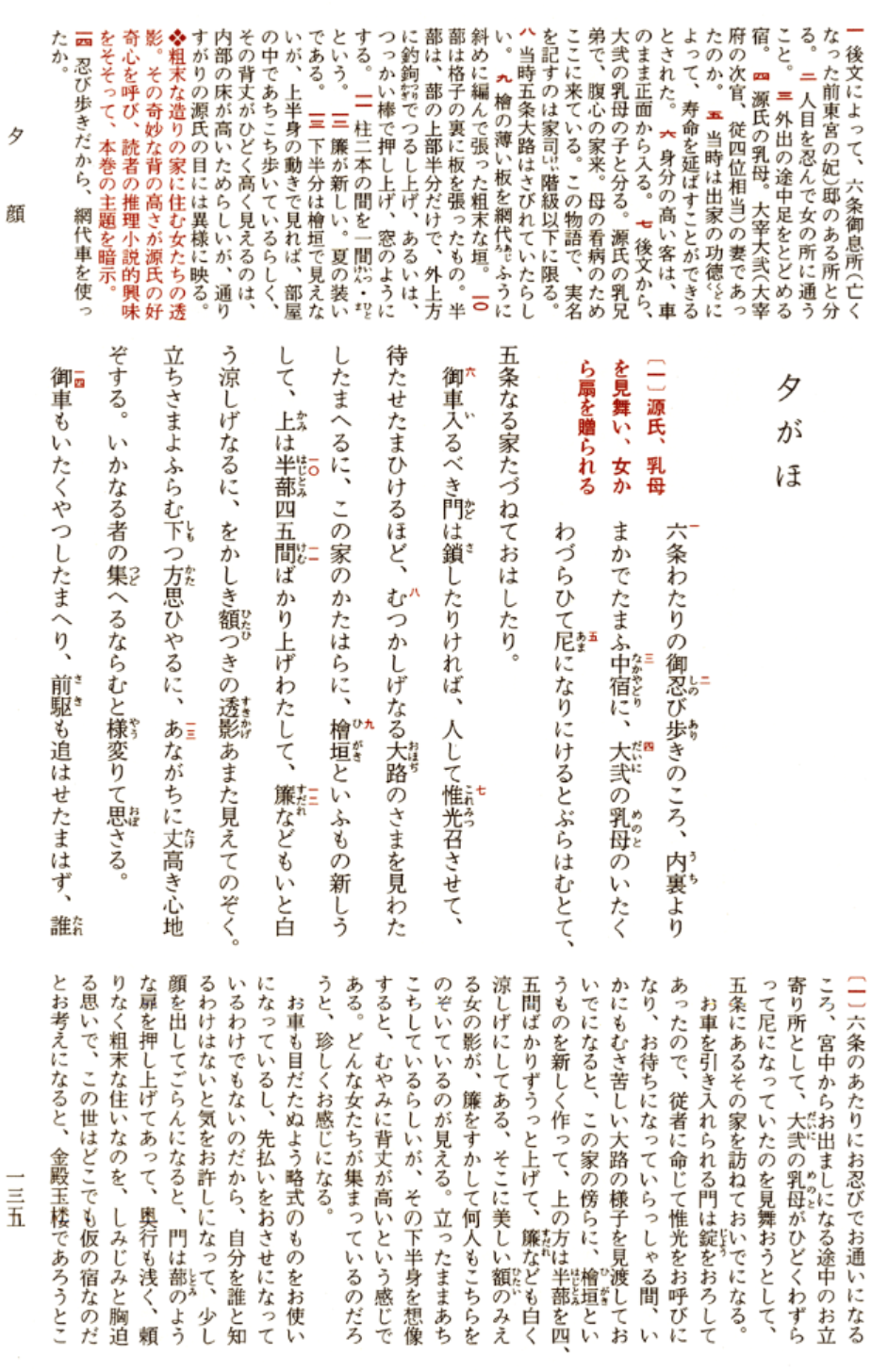

『須磨・心づくしの秋風』 「黒=原文」・ 「青=現代語訳」 解説・品詞分解はこちら 問題はこちら 須磨には、いとど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、 須磨では、ますます物思いを誘う秋風のために、海は少し遠いけれども、 行平の中納言の、「関吹き越ゆる」と言ひけむ浦波、夜々はげにいと近く聞こえて、 行平の中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだとかいう浦波が、夜ごとに実にすぐ近くに聞こえて、 またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。 たくさん。 」 と言う。
須磨への退居から二年半後、光源氏は都に呼び戻され、政界に復帰する。
(あなたの嫉妬は)だれが教えるのだろう。