妥当の類語・関連語・連想語: 連想類語辞典
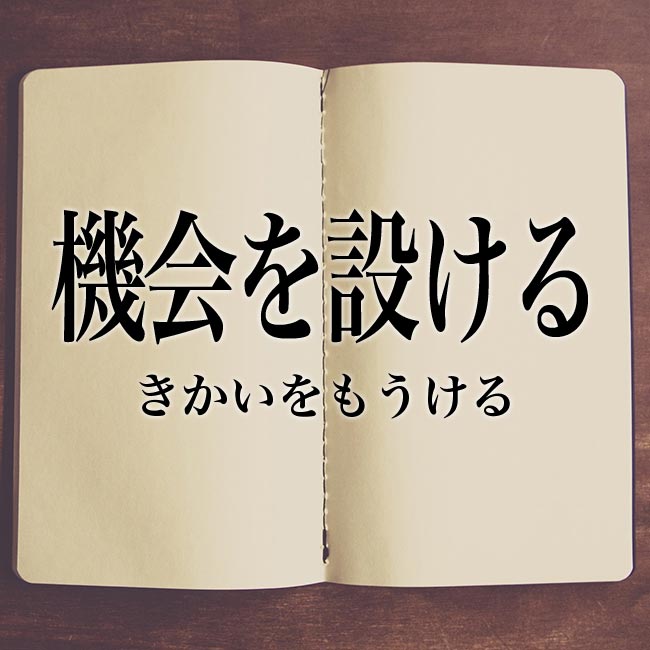
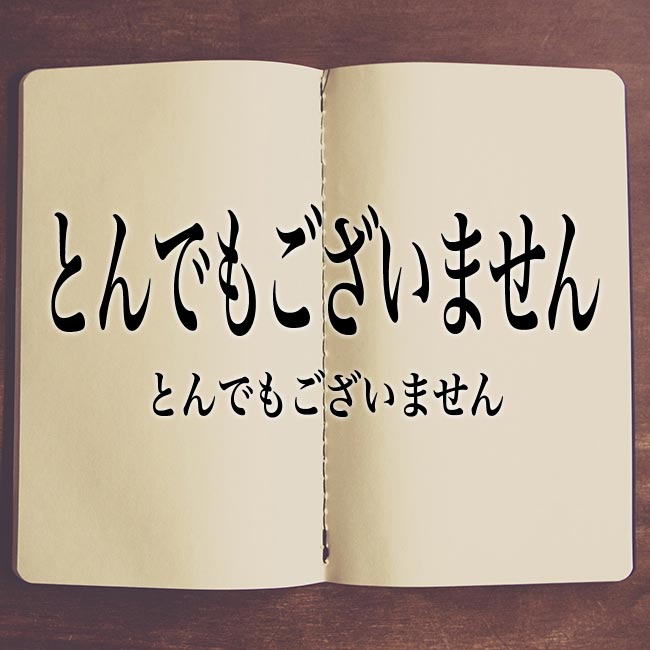
「適切」よりも「適当」の方が、範囲が広く、ある程度の幅があります。 、または似合う• 「いい加減」という意味も間違いではない 「適当」にはもうひとつ「いい加減」という意味もあります。
17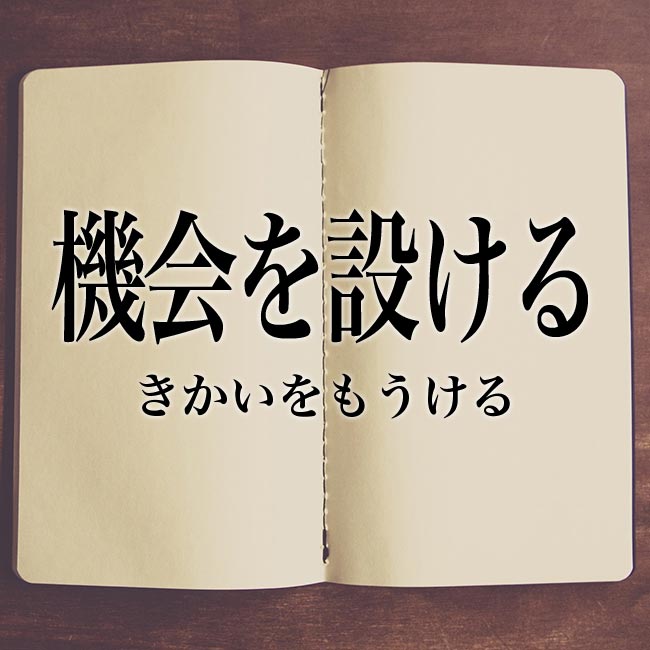
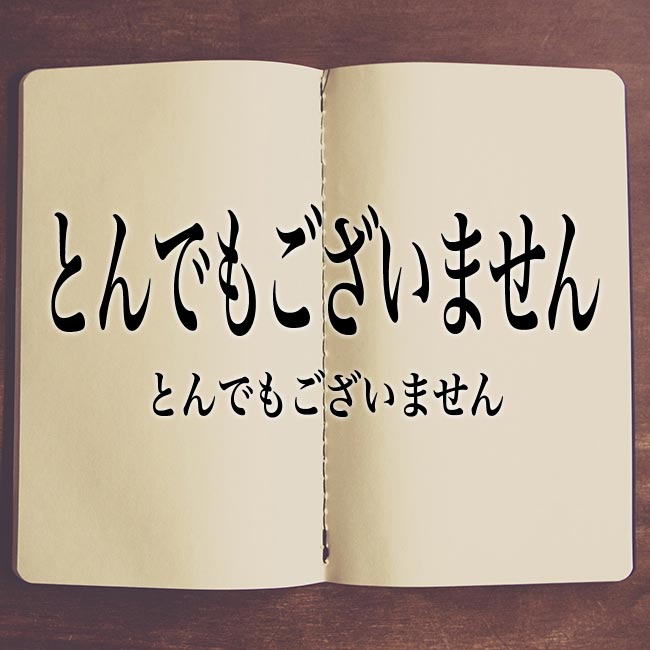
「適切」よりも「適当」の方が、範囲が広く、ある程度の幅があります。 、または似合う• 「いい加減」という意味も間違いではない 「適当」にはもうひとつ「いい加減」という意味もあります。
17企画ミーティングに参加したが、ほとんどが妥当な意見であった。
日常生活では、主にスポーツ関連のニュースなどで耳にする機会の多い言葉です。
久しぶりに知り合いと偶然街で出くわしたが、名前が出てこないので適当にはぐらかしておいた。
また、慣用表現として「This is going well(これは適当すぎる)」という表現もあります。
状況や目的などにぴったりあてはまることや、その場や物事にふさわしいことを意味します。
戦時中の日本では、戦争では様々な装備品が準備してあって、厳重に管理されていました。
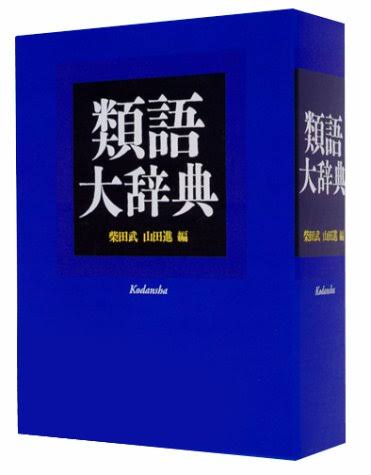
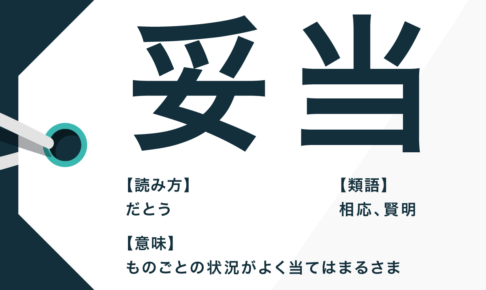
いい加減」という意味• 例文3や4の適切は、物事にふさわしいことを表しています。 また、そのさま) 「トラブルが発生した場合は、適宜お知らせします」 「いい加減」を意味 生半可 (意味:十分でなく中途半端であること) 「生半可な気持ちで挑んでいると、いつか失敗をする」 ぞんざい (意味:いいかげんに物事をするさま。
10「妥当」はものごとの状況や方法などがよく当てはまることを意味しますが、「適切」の場合は「ピッタリと当てはまること」となります。
投げやり) 「仕事をぞんざいにする」 いい加減 (意味:大雑把で徹底することなく、中途半端なさま) 「準備をいい加減にしていると、あとで困る」 投げやり (意味:物事をいい加減に行うこと。
みなさんは 「穏当」という言葉を知っているでしょうか。
また、「お小遣いはいくらが妥当なのか」とは、世間一般的な考え方ではいくらぐらいが正しいのか、を表しています。

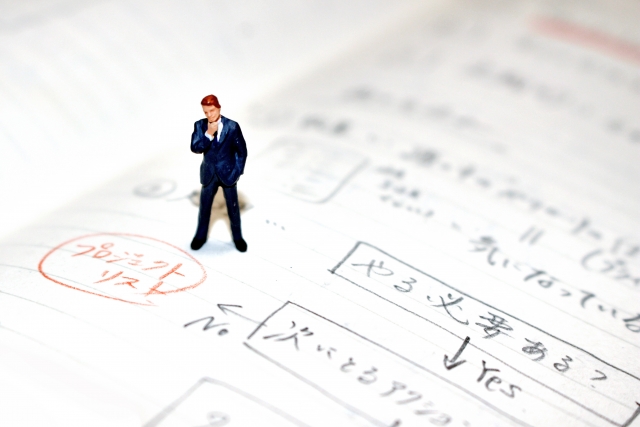
対等のものまたは目下に使う言葉。 適当な運動は健康に良い。 「適当」という言葉は、「ぴったり」というニュアンスでなく、あくまでも程度が『程よい』ということを意味しています。
10「適当」とは違い、「いい加減」「ほどほど」といった意味は含まれません。
日本語としての正式な表現ではなく、 携帯や漫画などで使われることが多い表現です。

宜しい• 仏教では、心と心所との関係について使われる場合が多く、心と心の働きとが互いに結びついていること、または心と対象世界との結合、因と果との結合、身・口・意の三業 さんごう の結合などにも使われます。 「当」は「あてはまる」「道理にかなう」を意味します。
17random(でたらめな)• つまり、ものごとの実情において「マッチする度合」が「適切」の方が高いということです。
たとえば、「このメンバーなら、君がリーダーなのは妥当かな」という言葉は、大いなる誉め言葉とはいえません。

vague(曖昧な) たとえば、「an irresponsible father」は「適当な父(無責任な父)」という意味で、「make a vague answer」は「いい加減な返事(曖昧な回答)をする」という意味となります。
15また、そのさま) 「この金額が妥当だと思われる」 適格 (意味:資格にかなっていること。
でないか端ではない• 「ほどよく当てはまること」と「程度などがほどよいこと」はほとんど意味は同じですが、他にも「いい加減」という全く逆の意味を持ちます。


「テキトー」とカタカナで表すと、「いい加減で、ゆるく、なんとなくでいいよ」という意味で、 「適当」と漢字で表すよりも雑な感じが強くなっている印象ですよね。 「妥当」は、他者や出来事に対して 「最良の状況」であると評価する言葉ではないことに留意しましょう。 「適当にやっておいて」と言われると「雑にやっておいていいよ」「いい加減にやっておいていいよ」という意味に解釈する人も多いのではないでしょうか。
20「穏当」と「妥当」の違い• この場合、依頼主の意図をくみ取り、求められた質のものを提出する必要があります。
「その場に合わせて要領よくやること。