新型コロナ、未だ手付かずの倫理的課題は? 専門家会議のメンバーが問いかける


特に、文科系からの領域架橋を応援すること。 米ブラウン大学研究員などを経て、13年より現職。
51999 Predictive testing of 25 percent at-risk individuals for Huntington disease 1987-1997 , American Journal of Medical Genetics. Harperらによると、イギリスのハンチントン病の発症前検査は、1997年までに2,937件が行われているが、全体の41. ただ、そのモラトリアム期間にあっても、「遺伝性疾患の明らかな家族歴がある場合に、検査を受けたかどうかを尋ねること」は例外として認められるとしている21。
だから、「全ての人にPCR検査をすることは、このウイルスの対策として有効ではありません」と言い切っています。


そのため、保険会社による検査結果の利用を監視するためのシステムを構築する必要がある」と結論付けていた。
「『肺炎』という時に、これぐらいの肺の病状だったら軽症だ、と医師の中でイメージがあるとしても、患者の方ではいろんな思いがあるとお聞きしています」 患者の体験談が散発的に報道されていることも、病気のイメージに影響を与えていると指摘する。
厚生労働省においては、(平成22年)よりレセプト情報等の提供に関する有識者会議の構成員を兼任している。


その点を次に述べたい。 特に精神障害の場合には、そのスティグマ(烙印)の大きさに留意しなければならない」と指摘し、「検査結果によって、どの程度の保険料の変更や加入者の増減があったのか、逐一政府に報告されるような監視システムを設けるべきである」と提案している。
まさにその通りだ。
研究への貢献をする試料提供者・被験者の「当事者性」に立脚し、「情報保障」を意識した研究者との対話実践に貢献すること。
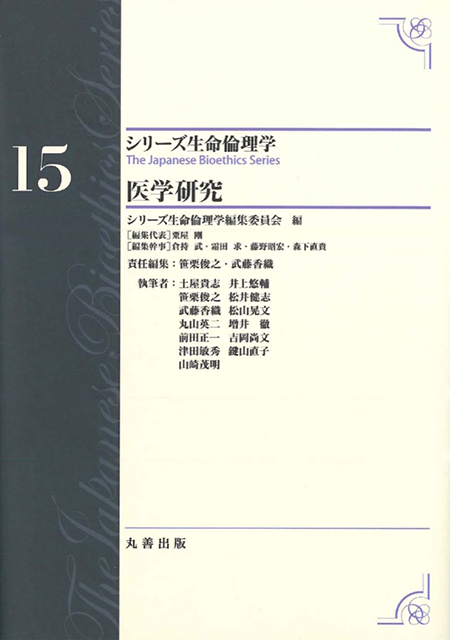

財団法人医療科学研究所研究員、米国ブラウン大学研究員、信州大学医学部保健学科講師を経て、07年より東京大学医科学研究所准教授、13年より現職。 メディアへの要望はたくさんあり過ぎます(苦笑)。
10(2)感染経路などについて これまでに判明している感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体です。
そういう意味で、専門家会議がこの見解を出した後、市民が信用してくれるかどうかはすごく怖かったです。


厚生労働省の対応を批判する記者の人たちも、感染拡大を予防する市民の一員として、それぞれが一日の行動パターンを見直して、感染防止策を徹底したうえで取材してほしいですね。
日ごろの研究内容と専門家会議構成員に加わった経緯を教えてください。
「ある日勇気を出して担当医師に『先生は私を何の病気だと疑っているんですか』と聞いたんです。

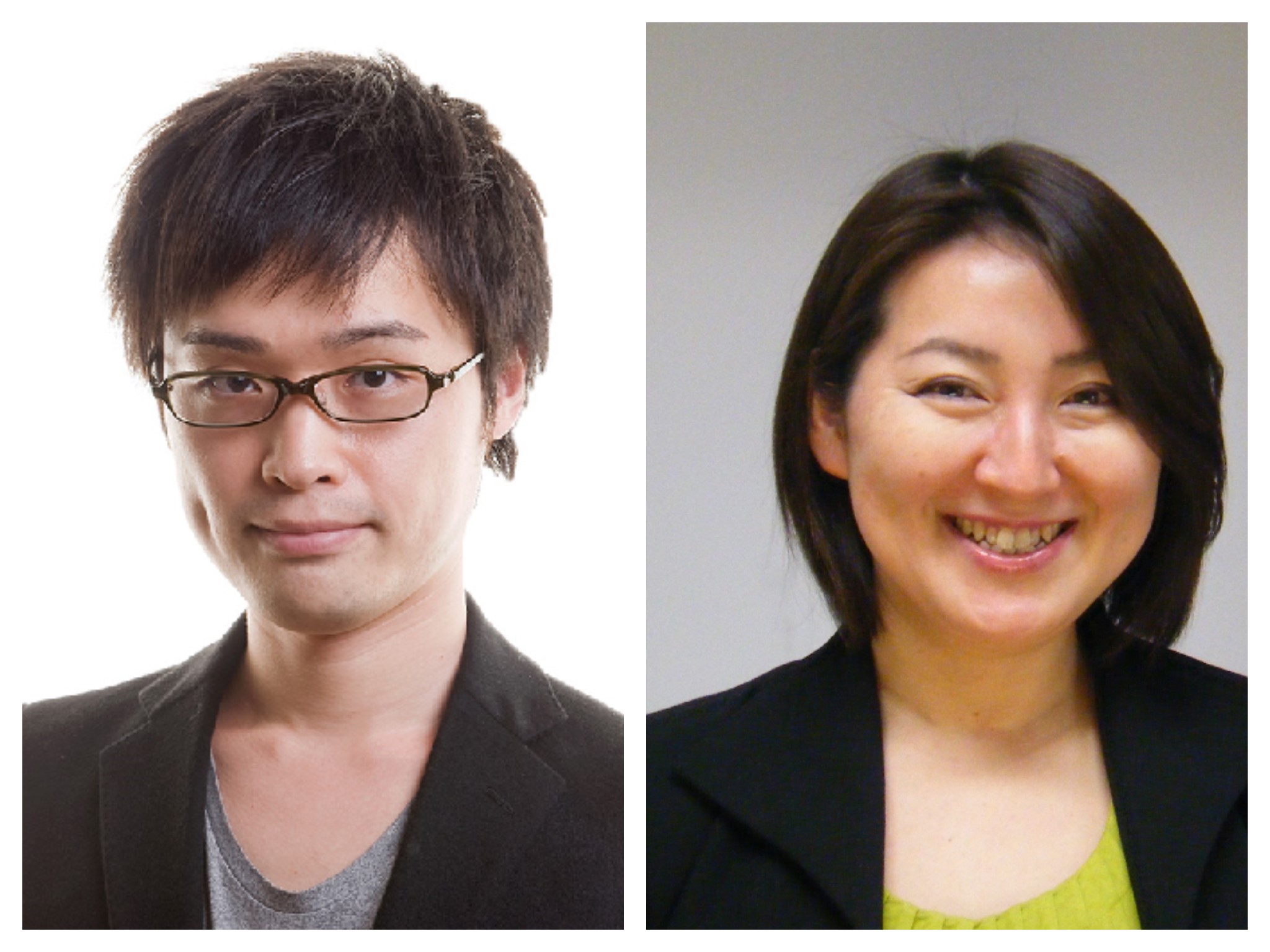
また、GAICとは別に、HGACの提案に沿ってUK Forum for Genetics and Insurance が設立された。 その後、に渡り、同年にのとなった。 保険会社は「95%の加入者が平均的な保険料で加入できるのに対して、残りの4%は高い保険料を提示され、1%は加入謝絶される」というデータを提示しているが20 、Lowらは、コントロール群として一般の人々を対象に行った調査結果と照らし合わせてみても、そのとおりの比率の結果になったと判断する。
20この専門家会議は、成り立ちは違うけど、そういうミッションを負っているよね、という点は、他の委員のみなさんも全員賛同してくださって、週末もずっとメンバーで練ってまとめました。
そしたら声を荒げて『悪性リンパ腫だよ!』と言われました」。