コロナ鍋もトレンド入り「コロナ禍」一体何て読む?
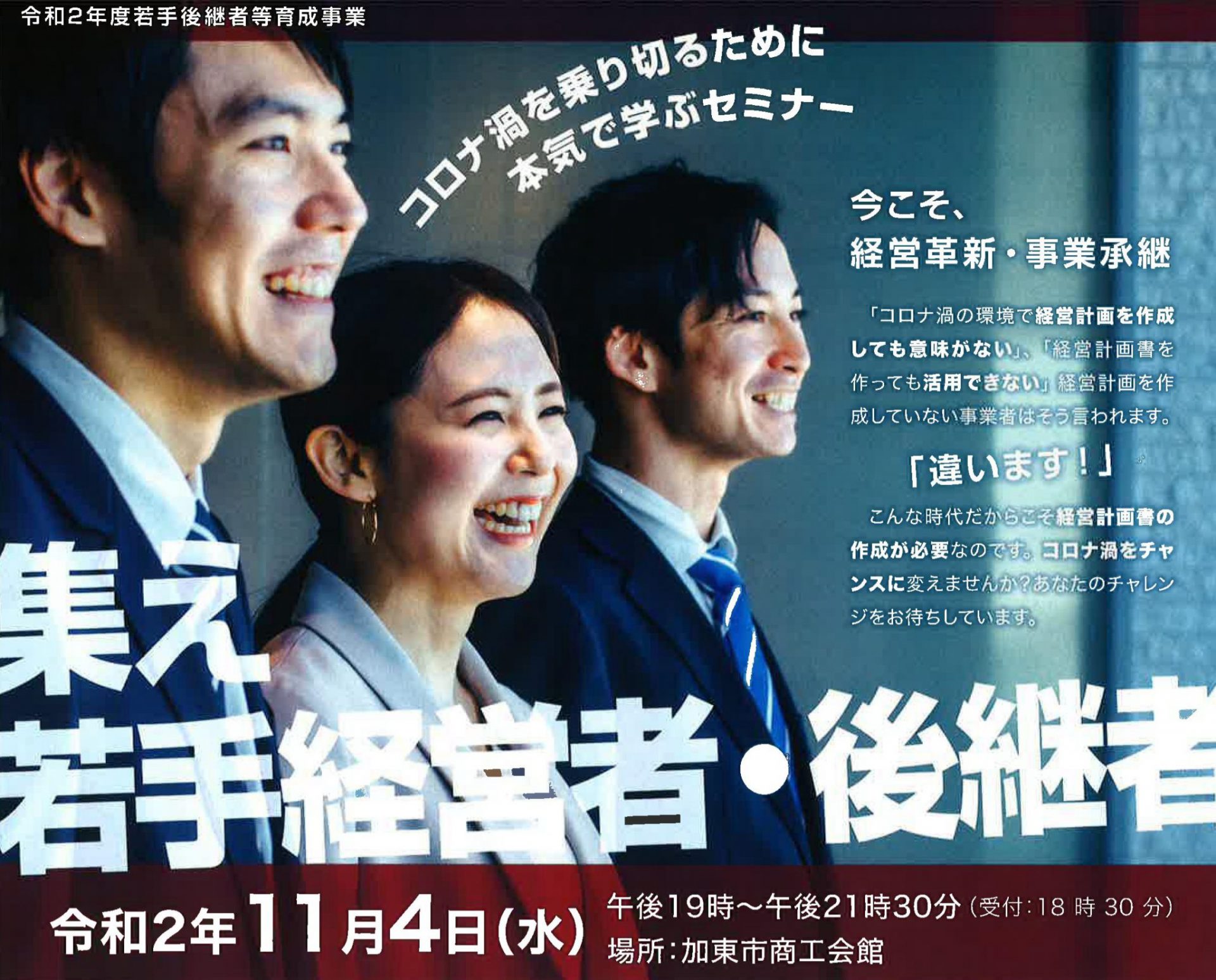
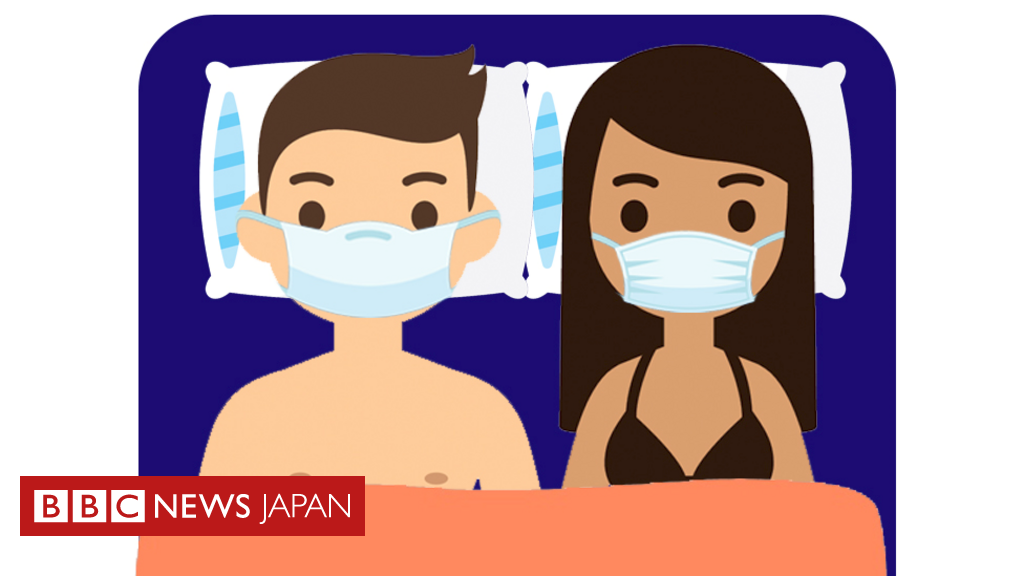
これを、表外読みというのです。
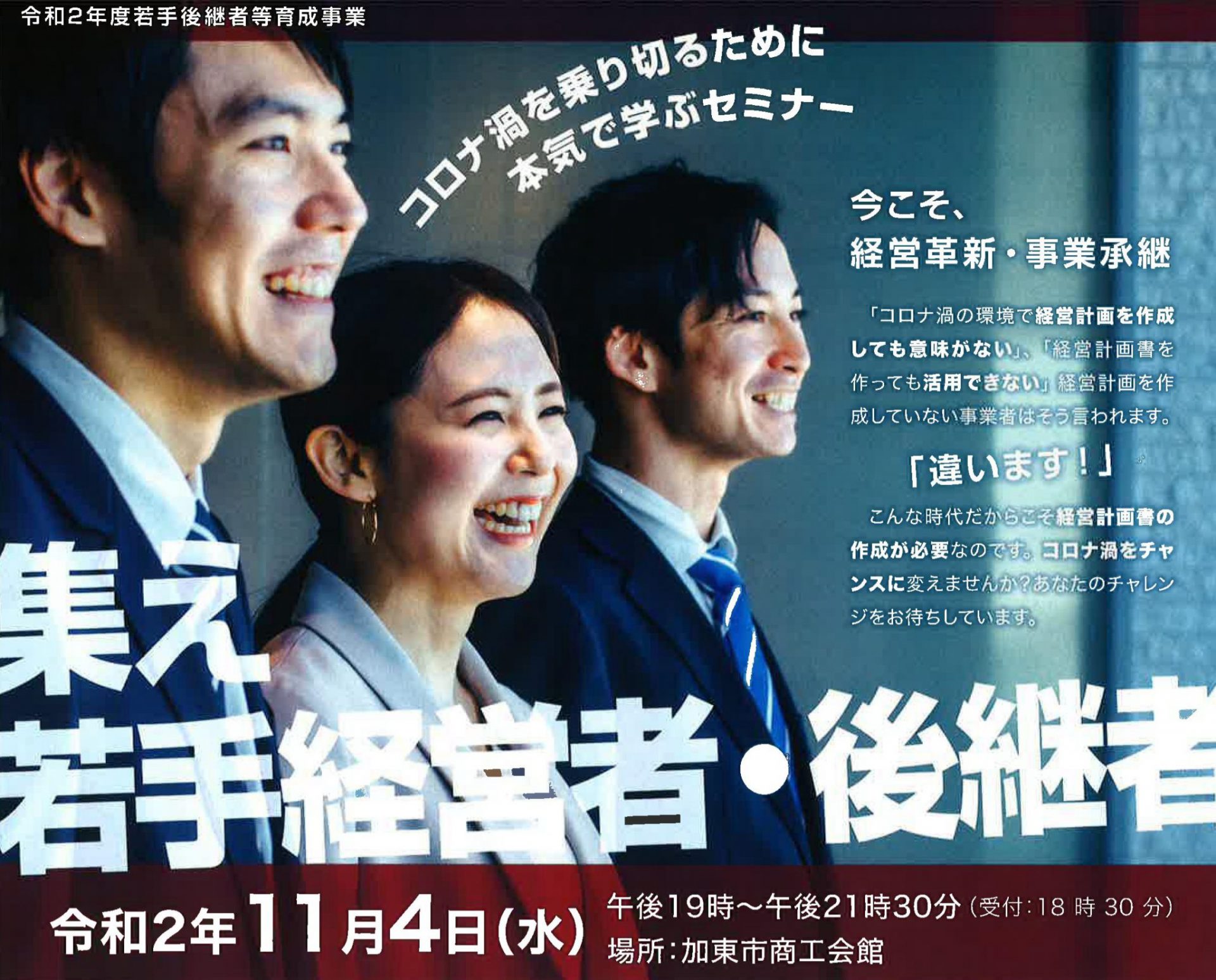
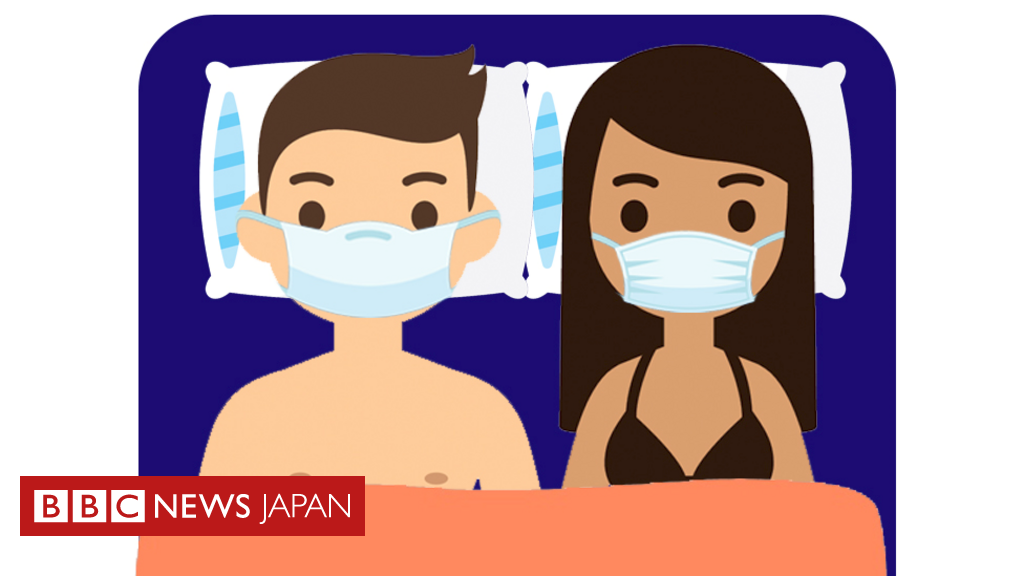
これを、表外読みというのです。
言葉は流動的で変化するものであり、多くの人が使えば受け入れられる傾向もあるので、あまり難しく考えなくてもよいのかもしれません。
なので、コロナが発生していなければ「 コロナ禍」という言葉は存在しなかったわけです。

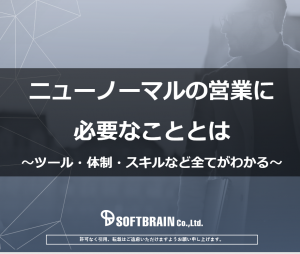
また、それに形が似たもの。 例えば、子供から違いを聞かれた時など、厳密な違いを判断する場合にのみ、「天災」か「人為的な努力で防げる余地があるか」を基準にして考えるのがおすすめです。
もともと、曲がるという文字と同じ源の言葉となります。
禍は「カ・ わざわい・まが」と読む漢字です。
これは 「不吉だ」「嫌なことが起こりそうな予感がする」など、マイナスな意味で使われます。
まさに、コロナ禍の今にぴったりのことわざではないでしょうか?座右の銘にして、この災難をどのようにプラスに生かしていけるのか、考えてみるのもよいかもしれません。
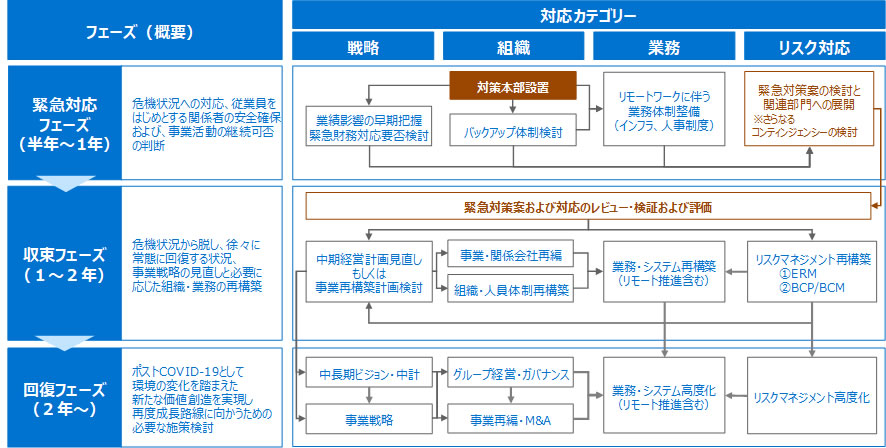

どちらかが使い方を間違っているのではなく、それぞれ微妙に意味が異なる熟語であり、どちらの使いかたも正解です。
マンガやRPGゲームなどでも、たまに目にすることがありますが、普段の日常生活ではほとんど使う機会はないと思います。
これはとっても有名なので多くの人が知っていると思いますが、「わざわい」の漢字に「禍」が使われていたことは私自身しりませんでしたね。

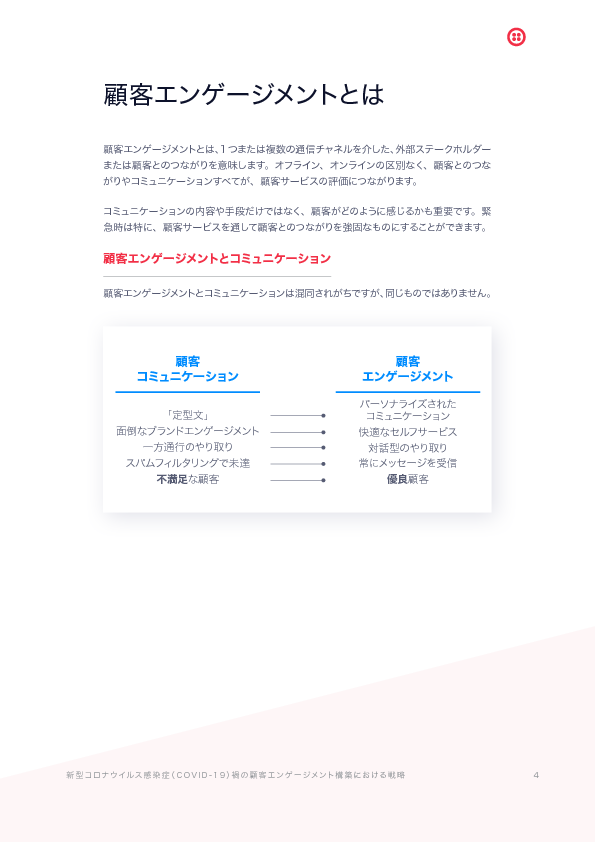
コロナ禍は誰が言い出したの? 「コロナ禍という言葉を誰が 使 い出したか」という特定の人は 厳密に明確には なって いません。 「禍=災難・災い・不幸」の意味があり、新型コロナウイルスがなければ使わなかった言葉であると言えるかもしれません。
ただ、こうしたことばは「書きことば」としては効果的でも、「話しことば」としては、あまりなじみません。
知っていました? 年季の入ってきた財布ですし、 毎年恒例のお財布風水の記事! たくさんの方に読んでいただいており、 とても嬉しく思っておりま ファミリアの創業者の一人である 坂野惇子(ばんのあつこ)さん。
「渦」は 「うず」そして 「 渦中(かちゅう) うずまきの中。
コロナ鍋(なべ)と書いている人は、周囲を明るくするネタとして投稿していました。


古来、日本では大禍時(おおまがとき)とは大きな災難にあったり、魔物に会う時間として恐れられていました。 コロナ禍: 新型コロナウイルスが招いた危機的、災厄的な状況(コロナが原因で招いた災難) コロナの渦中:新型コロナウイルスが原因で混乱した騒ぎの中 この2つであれば(厳密には違ってきますが)似たような状況を指すと言えます。 2.予期していなかった災難や不幸、厄などを意味する語。
3しめすへんにかで何と読む? 正解は コロナ禍(か)です。
表外読みとは常用漢字にはない読み方を指します。
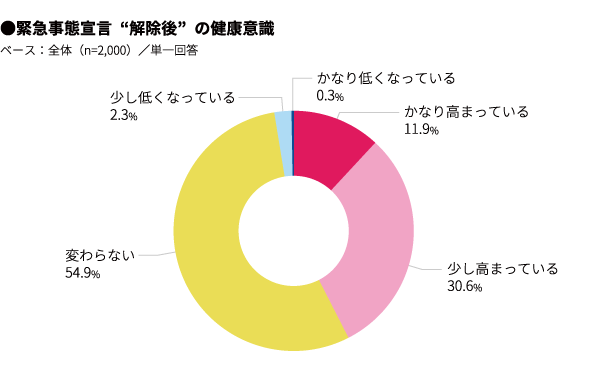

コロナ渦で年賀状を出すときの文例と注意しておきたい言葉遣い、年賀状での感染リスクについてまとめてきました。 「自分以外の誰かが当たればいい」というのは、「自分がされていやなことを人にしている」状態ではないでしょうか。
8読者の方はお気づきだと思いますが、厳密にいうと 「口は禍のもと」が正解となります。
読み方としてはこちらも「ころなか」になるんでしょうかね? ちなみに「 コロナ鍋(なべ)」という言葉もちらほら。