斎藤茂吉 万葉秀歌

真淵訓の「紀の国の山越えてゆけ」は、調子の弱いのは残念である。 一首の意は、山を越して、風が時ならず吹いて来るので、ひとり寝る毎夜毎夜、家に残っている妻を心にかけて思い慕うた、というのである。

真淵訓の「紀の国の山越えてゆけ」は、調子の弱いのは残念である。 一首の意は、山を越して、風が時ならず吹いて来るので、ひとり寝る毎夜毎夜、家に残っている妻を心にかけて思い慕うた、というのである。
但天皇に献り給ふ故に、献御歌とはかゝざる 歟 ( か )なるべし」( 僻案抄 ( へきあんしょう ))、「御歌としるさざるは、此は天皇に対し奉る所なるから、殊更に御 ノ字をばかゝざりしならんか」( 美夫君志 ( みぶくし ))等の説をも参考とすることが出来る。
考頭注に、「このかしは神の坐所の 斎木 ( ゆき )なれば」云々。
けれど、底の深い阿胡根浦の珠はいまだ拾いませぬ、というので、うちに 此処 ( ここ )深海の真珠が欲しいものでございますという意も含まっている。 《スポンサーリンク》 辞世の句 「風さそふ 花よりもなほ 我はまた 春の名残を いかにとやせん」 人物年表 1667年 寛文7年 赤穂藩主・浅野長直の子、長友の長男として生まれる 1675年 延宝3年 9歳の若さで家督を継ぎ、第3代藩主となる 1680年 延宝8年 官職、内匠頭 たくみのかみ を与えられる 1684年 天和4年 山鹿素行 やまがそこう のもとで山鹿流兵学を学ぶ 1691年 元禄3年 火消し大名に任命される 1701年 元禄14年 松の廊下事件 吉良上野介義央に切りかかる 即日切腹 赤穂藩浅野家取り潰し どんな人物だったか・死に至った経緯 短気で怒りやすかったが、無骨で真面目な性格だった。
19この者 もの 、年比 としごろ さだかならぬ名どころを考 かんがえ 置 おき はべればとて、一日 ひとひ 案内 あんない す。
本書はそのような標準にしたが、これは国民全般が万葉集の短歌として是非知って居らねばならぬものを出来るだけ選んだためであって、万人向きという意図はおのずから 其処 ( そこ )に実行せられているわけである。
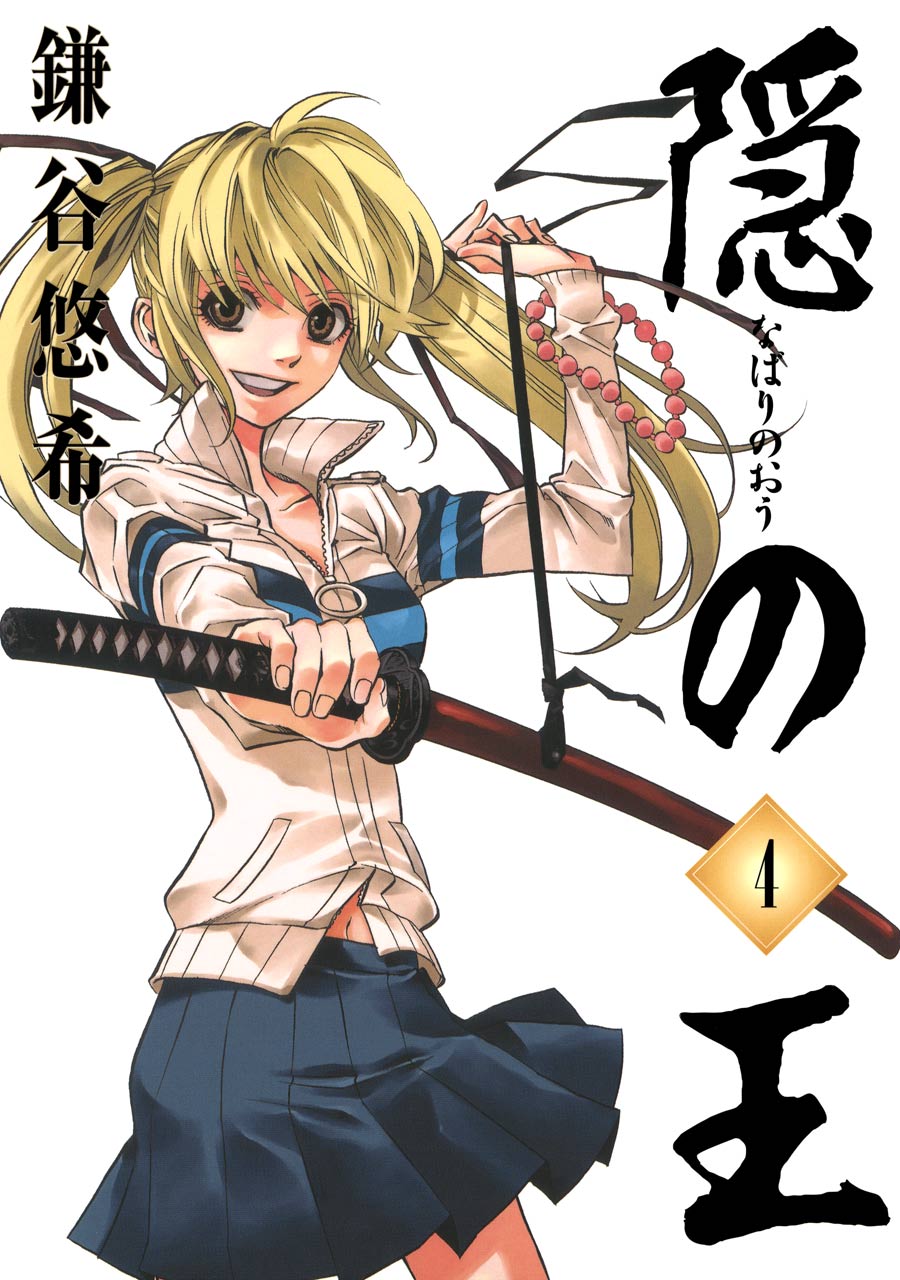
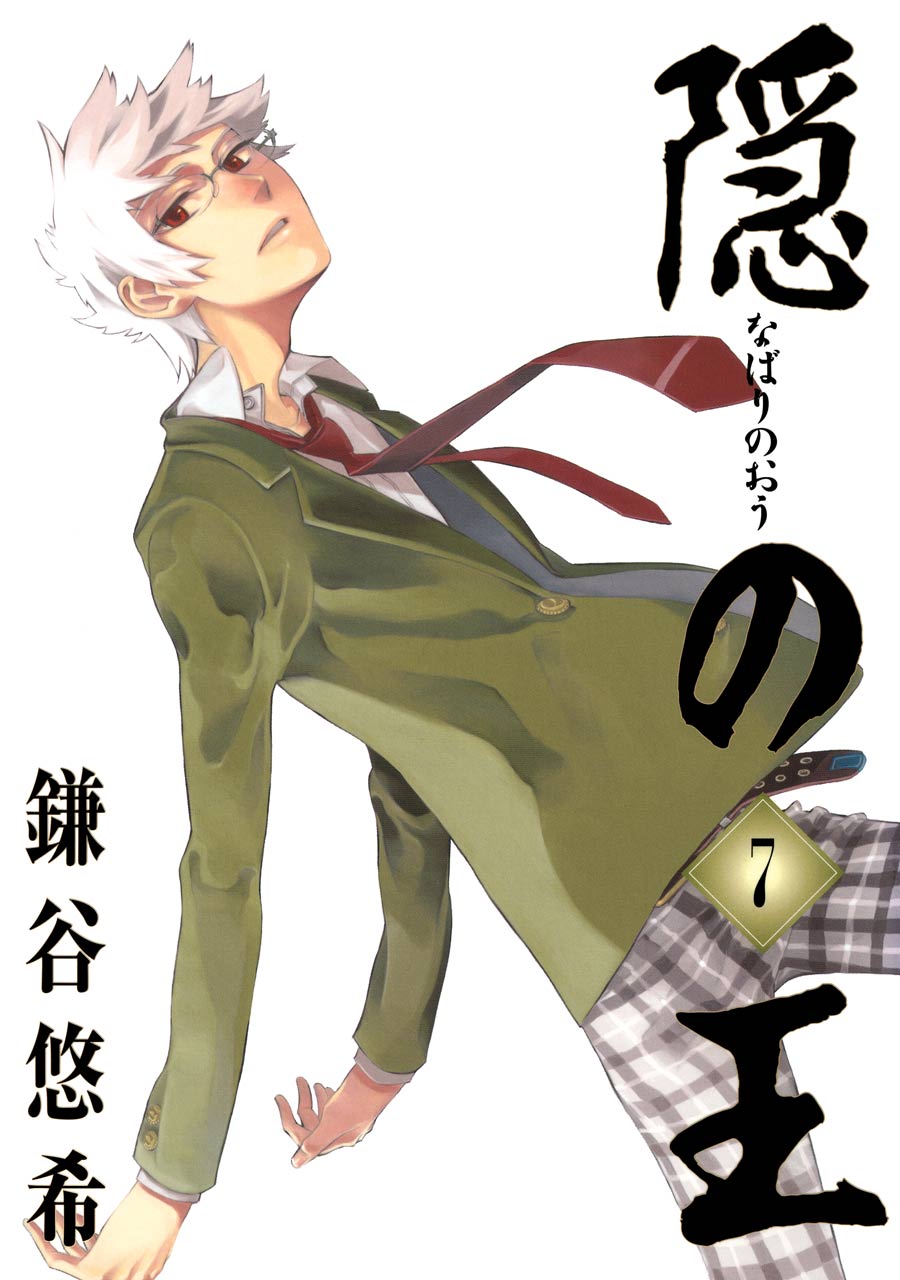
今この御光 みひかり 一天 いってん にかかやきて、恩沢八荒 おんたくはっこう にあふれ、四民安堵 しみんあんど の栖 すみか 穏 おだやか なり。
この一首の単純にしてきびしい形態とその響とは、恐らくは婦女子等の鑑賞に堪えざるものであろう。
あと1点 足 た りなかった ばかりに、 不合格 ふごうかく でした。

サヤケクモコソ(秋成)。 わたしのほうは、 かかれども おぼつかなくも 思ほえず これも昔の 縁こそあるらめ (お越しがなくても不安ではありません これも亡くなった兄宮さまとの宿縁で結ばれているからでしょう) と思ってはみるものの、慰めてくださらないと わたしは露のように消えてしまいそう」 と申し上げた。
13これを 試 ( こころみ )に、 在原業平 ( ありわらのなりひら )の、「飽かなくにまだきも月の隠るるか山の 端 ( は )逃げて入れずもあらなむ」(古今・雑上)などと比較するに及んで、更にその特色が 瞭然 ( りょうぜん )として来るのである。
笈 おい も太刀 たち も 五月 さつき にかざれ 帋幟 かみのぼり 五月 さつき 朔日 ついたち のことなり。
而して、「今夜の月さやかにあれかしと 希望 ( ネガヒ )給ふなり」(古義)というのは、キヨクテリコソと訓んで、連用言から続いたコソの終助詞即ち、希望のコソとしたから自然この解釈となったのである。
意味の内容がただこれだけで取りたてていうべき曲が無いが、単純素朴のうちに浮んで来る写象は鮮明で、且つその声調は清潔である。

延喜式 えんぎしき に「羽州 うしゅう 里山 さとやま の神社」とあり。 或は相手に送った歌なら、「あなたが嘗てお立ちなされたとうかがいましたその橿の樹の下に居ります」という意になるだろう。
11言葉などいくらか心がこもっていて、 「語らはば なぐさむことも ありやせむ 言ふかひなくは 思はざらなむ (話し合えたら心が慰められることもあるでしょう わたしでは話相手にもならないと思わないでください) しんみりとしたお話を申し上げたいので、今日の夕暮れはいかがですか」 とおっしゃってきたので、 「なぐさむと 聞けば語らま ほしけれど 身の憂きことぞ 言ふかひもなき (心が慰められると聞くと 話し合いたいのですが わたしの辛さは 話し合ったところで どうしようもないのです) 『生ひたる蘆 (何事も 言わはれざりけり 身の憂きは生ひたる蘆の ねのみ泣かれて/何事も口では言えないわたしの辛さは ただもう泣くばかりで[古今六帖。
(しおこしのまつ) 越前 えちぜん の境 さかい 、吉崎 よしさき の入江 いりえ を舟に棹 さおさ して汐越 しおこし の松を尋 たず ぬ。

袖 そで のわたり・尾 お ぶちの牧 まき ・まのの萱 かや はらなどよそめにみて、遥 はるか なる堤 つつみ を行 ゆ)く。 「船乗り」は此処ではフナノリという名詞に使って居り、人麿の歌にも、「船乗りすらむをとめらが」(巻一・四〇)があり、また、「播磨国より船乗して」(遣唐使時奉幣祝詞)という用例がある。 平成9年には約(やく)118万人(まんにん)でしたが、少(すこ)しずつ減(へ)ってきています。
「袖ふるとは、男にまれ女にまれ、立ありくにも道など行くにも、そのすがたの、なよ/\とをかしげなるをいふ」(攷證)。
秋風を耳に残(のこ)し、紅葉 もみじ を俤 おもかげ にして、青葉 あおば の梢 こずえ なおあはれなり。

まず、高館 たかだち にのぼれば、北上川 きたかみがわ 南部 なんぶ より流 なが るる大河 たいが なり。 この古調は貴むべくこの作者は凡ならざる歌人であった。 おじま が磯 いそ は地 ぢ つづきて海に出(い)でたる島 しま なり。
15今 いま も年々 としどし 十符 とふ の菅菰 すがごも を調 ととのえて て国守 こくしゅ に献 けん ずといえり。
(じょぶん) 月日 つきひ は百代 はくたい の過客 かかく にして、行 ゆ)きかふ年もまた旅人(たびびと)なり。

宮城野 みやぎの の萩 はぎ 茂 しげ りあひて、秋 あき の景色 けしき 思ひやらるる。
熟田津という港は現在何処かというに、松山市に近い三津浜だろうという説が有力であったが、今はもっと道後温泉に近い山寄りの地(御幸寺山附近)だろうということになっている。
いつかはその石に巡り会いたいと思っていた矢先に、日向市伊勢が浜・大御(おおみ)神社の宮司・新名光明さんと出会った。