労働基準監督署の所在地・管轄一覧
首都圏青年ユニオン連合会は、雇用契約に付随して締結せざるを得なかった講習受講費用の支払い義務に関する不存在確認を団体交渉で明確に話し合っていきたいと思います。
首都圏青年ユニオン連合会は、雇用契約に付随して締結せざるを得なかった講習受講費用の支払い義務に関する不存在確認を団体交渉で明確に話し合っていきたいと思います。
職務遂行能力には、個人差が大きい。
徴収職員である厚生労働事務官は、各人が独立した権限をもち、(都道府県によって異なる場合もあるが)おおむね労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険徴収課(室)と所轄の労働基準監督署に配置されて、滞納処分と滞納整理に関する事務を行っている。
年々、厚生労働事務官・厚生労働技官とともに、労働基準監督官も減員されているのが現状である(新人事制度では、労働基準監督官が監督・安全衛生・労災補償を、厚生労働事務官が労働保険適用徴収・業務(庶務会計)に当たることとされて、厚生労働技官の今後の採用はなくなっている)。
労災課 労働者災害補償保険の給付事務、労働保険料の徴収を行う。
局総務課の総務・人事係長、局企画室の企画係長、局監督課の監督係長の経験者は、将来を嘱望されている労働基準監督官のエース的存在であり、その後、局監察監督官や労基署長などのポストを務め、最終的には筆頭署長に昇進していく。
)、監督・安全衛生担当には労働基準監督官(なお、厚生労働技官は次長にはなれない)が、労災補償・業務担当には厚生労働事務官が就任する(労働基準監督官、厚生労働技官の就任も可能)。
課長には、労働基準監督官が就任する。
三課制署 三つの課が置かれている労基署の課は、次のとおりである。

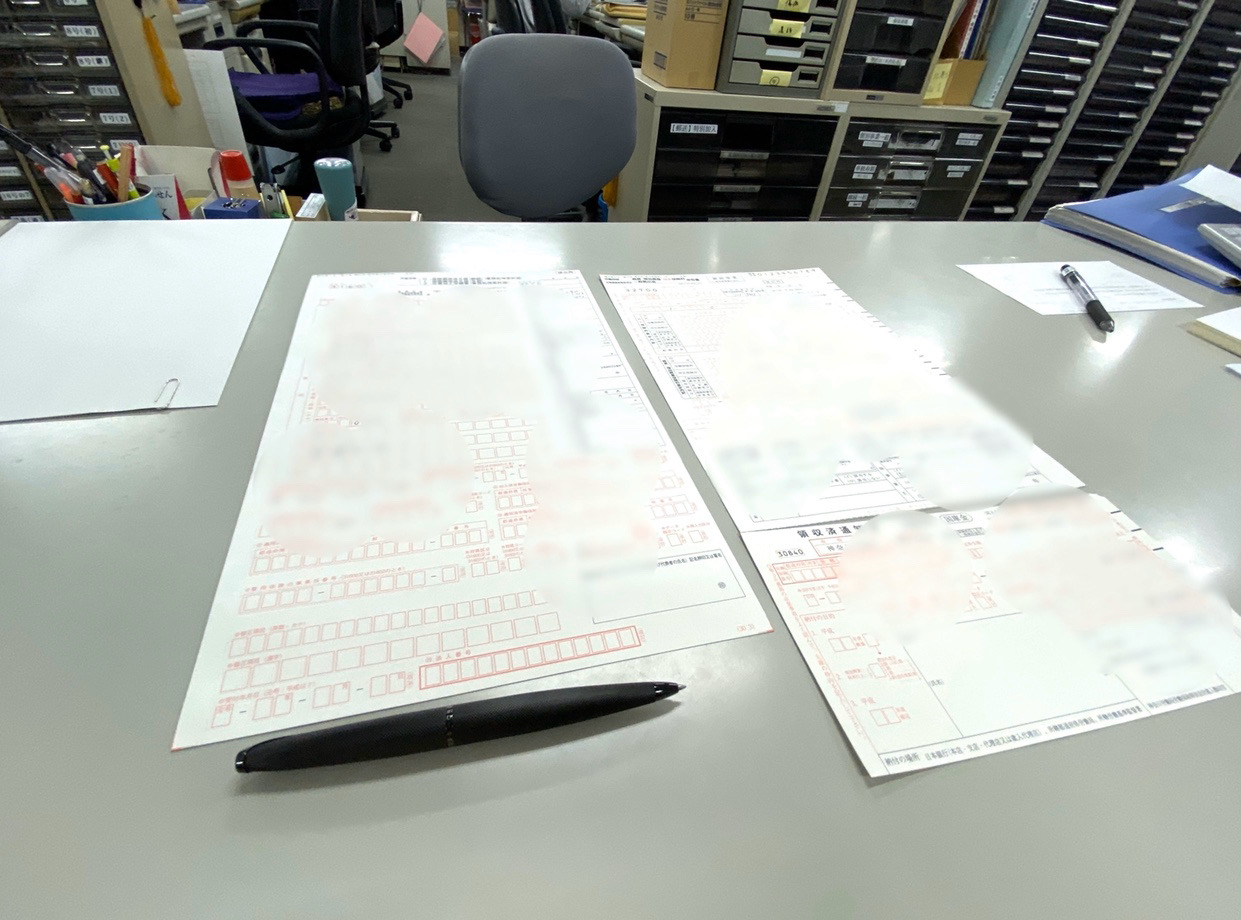
例外として、国家公務員II・III種試験に合格して都道府県労働局に採用された、おおむね50歳以上の厚生労働事務官・厚生労働技官が労働基準監督官に任命されて(政令監督官という)、労基署長を務めることもある。
4)に関すること。
新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合 【適用猶予事業・業務(建設事業、自動車運転の業務、医師等)】 時間外労働・休日労働に関する協定届等 労働基準法第139条~142条等(労働基準法第36条第1項の読み替え) 労働基準法施行規則第70条第1項 使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定等を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度です。
二課制署 二つの課が置かれている労基署の課は、次のとおりである。
5課長には、厚生労働事務官または厚生労働技官が就任する。
課長には、労働基準監督官が就任する。
労働基準監督署には監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、職員は(主に監督業務を担当)、厚生労働事務官(主に業務や庶務を担当)、(安全衛生業務担当)等からなる。 業務課 庶務、庁舎管理、賃金構造基本統計調査、会計、労働者災害補償保険の保険金支払を行う。
5(3)特別支給金則の一部改正 労働者災害補償保険特別支給金支給規則に基づく申請の一部について、記載事項に 個人番号を追加する。
- 外部リンク [ ]• 課長には、厚生労働事務官または厚生労働技官が就任する。