ことわざ「多勢に無勢」の意味と使い方:例文付き


「寡」は寡婦等で使われますから、一人と言う意味です。


「寡」は寡婦等で使われますから、一人と言う意味です。
2020-12-10 20:03:22• これも少数では多数にかなわないことのたとえです。
寡は衆に敵せず かはしゅうにてきせず :多数と少数では戦いにならないということ。


しかし、世の中には、相手と味方で人数差がある状態で戦うことがあらゆる場面であります。 ある戦 いくさ において、大人数に対して、武士の精鋭たち数人で挑んだ。 英語らしい比喩を用いたフレーズを紹介します。
11多勢に無勢まとめ ここまで多勢に無勢の意味や使い方を見てきました。
意味は「戦いで相手が多人数に対し少人数だと敵対できない」 「多勢に無勢」とは「相手が多人数に対し、こちらは少人数なので、敵対することは困難である」という意味を持ちます。


例えば、学校での話し合いや、友達との付き合い、会社でのミーティングなどです。 また、無も「む」と読むことが多いですが、ここでは「ぶ」と読みます。
16話し合いの場面をイメージしてみます。
そんなもの諺になりません。


賛成か反対で意見が割れました。 *ただご質問文を読むと「多勢に無勢」を「多勢VS無勢」ではなく「多勢+無勢」は多いか?少ないかとも受け取れますので、その解釈でも回答致します・・・「多勢」+「無勢(一人以上}」=多い(多い人数+1以上はやはり多い人数ですから) ご納得して頂ければ幸甚です。
14まとめ 以上、この記事では「多勢に無勢」について解説しました。
しかし「寡をもって衆を制す」ということわざもあるので、少ない人数でも力を合わせて工夫すれば大人数に勝つこともあるのかもしれませんね。
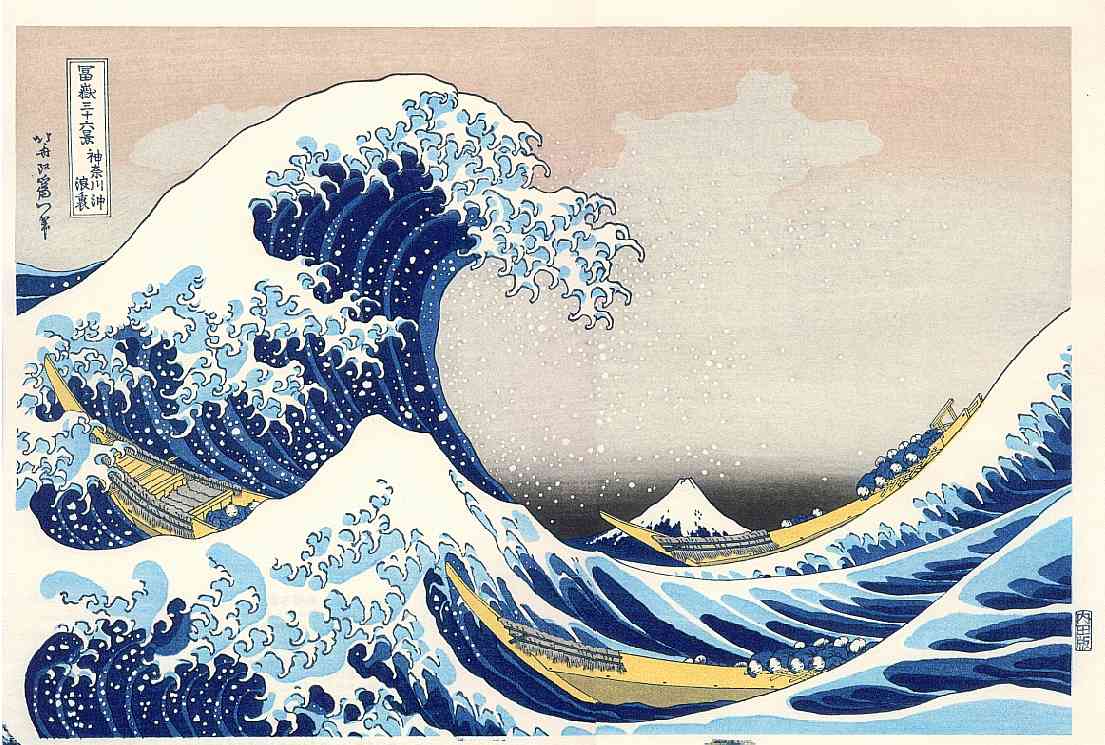

ネット上で多くの批判的な声が上がれば、瞬く間に同意見が拡散し、事の発端をつくった人(少数派)はあまりにも分が悪い状況に追い込まれます。
4更新された記事• 通常ドラマでは少数が多数を打ち破る子も珍しくありませんが、通常多勢に無勢の場合は勝ち目がない状態を指します。
日常生活というよりはドラマで聞く機会が多い言葉です。


また、 SNSいじめ・ ネットいじめといったものも、ある種の「多勢に無勢」的な状況に陥った結果として起きることでしょう。 しかし、人数は多いに越したことはありません。 「多勢に無勢」は英語で「Many a sheep drive away a wolf」 英語では比喩的な表現を使うことが多いですが、「多勢に無勢」も然りで「大勢の(おとなしい)羊は一匹のオオカミを追いやる」という意味の「Many a sheep drive away a wolf」と表現します。
6多勢に無勢というように、少人数では勝ち目がないこともあるでしょう。
戦いに負けた後に、「相手の方が人数が多く、ずるかった」「相手は人数多いから勝って当たり前だ」といった感じです。