倉敷市社会福祉協議会/障がい福祉課/倉敷市
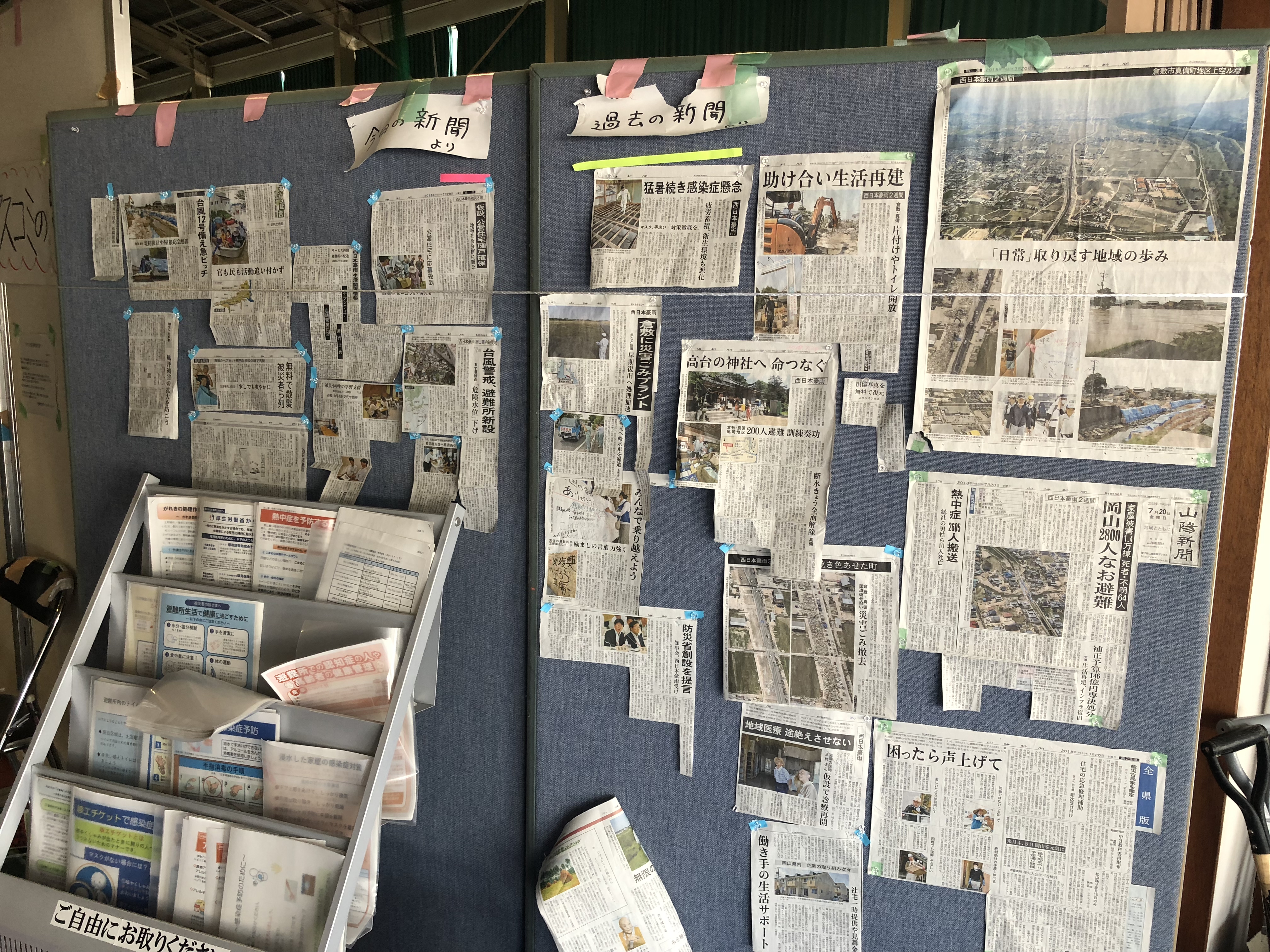
また、今回は、みなさんにサロンを紹介するための事例集を作り、配りました。 講演終了後は4つのグループに分かれて情報交換会。
9その中で、個人情報保護法ができたことによって、「なかなか情報がもらいにくくなった」「情報の共有をしてもいいのか不安がある」「そもそも個人情報保護法がよくわからない」というような声が多く聞かれました。
上成地区社協では毎年、栄養改善委員の協力を得て「おはぎ」を作り、それを持って民生委員が中心に訪問活動を行っています。


車椅子を借りに来られる方は、ピカピカの車椅子を見ると喜ばれます。 〔郵送について〕 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付が、 ・令和3年の2月までに終了された借受人の方(世帯)へは、2月末までに送付予定。 被害防止対策は「 即決をしない」 子どもや孫に確認を取ったり、親戚やご近所の方に相談したりして、一呼吸入れると冷静になれて被害を未然に防ぐことが出来るそうです。
18。
サービスのしくみ サービスの内容 家事援助サービス• 「岡山県西部ヤクルト販売株式会社」の皆さんは、毎年私たち倉敷市社会福祉協議会に車椅子を寄附してくださっています。
当日は相談会と同時に成年後見制 度基礎講座、市民後見人交流会も 開催されました。
身障スマイルの皆さん、本当にありがとうございました。

倉敷たすけあいサービス あなたの笑顔が私の安心 このサービスは、お年寄りや心身に障がいを持つ方、父子母子世帯や妊産婦の方などが、日常生活上の家事や介助で困っているとき「困ったときのたすけあい」の心を持った地域の人々(協力会員)がそのお宅を訪問し、身のまわりのお手伝いをする事業です。
712月2日(金)に倉敷市児島支所において、「個人情報の取り扱いに関する研修会」を開催しました。
今後も、このような研修会を各小学校区において開催できるように調整していきたいと思います。


身障スマイルの皆さんは、昨年6月に倉敷市社会福祉協議会に対して行った清掃活動を皮切りに、芸文館や市民会館、図書館、美術館、ライフパーク倉敷などに設置されている車椅子も清掃してこられたとのこと。 発足にあたり、平成30年度から 小地域ケア会議で、地域の福祉課 題の解決に向けた話し合いや活動 を展開することで、福祉の町づく りを推進していこうと、何度も話 し合いを重ねて設立されました。 名称 所在地 電話・FAX 地域福祉課 笹沖180番地 (くらしき健康福祉プラザ内) TEL 086 434-3301 FAX 086 434-3357 倉敷ボランティアセンター TEL 086 434-3350 FAX 086 434-3357 日常経済生活サポートセンター TEL 086 434-3364 FAX 086 434-3357 水島事務所 水島北幸町1-1 水島支所3階 TEL 086 446-1900 FAX 086 440-0154 児島事務所 児島小川町3681-3 児島支所4階 TEL 086 473-1128 FAX 086 470-0054 玉島事務所 玉島阿賀崎1-1-1 玉島支所2階 TEL 086 522-8137 FAX 086 523-0054 船穂事務所 船穂町船穂1861-1 TEL 086 552-5200 FAX 086 552-9030 真備事務所 真備町箭田1161-1 TEL 086 698-4883 FAX 086 698-9622. 開会の後、『ちょっと学習』ということで、児島警察署生活安全課の木村浩之課長に「高齢者を狙う身近なトラブル」という演題でご講演いただきました。
この「おはぎ」を持っての訪問活動は、もう20年以上続いており、対象者の皆さんも毎年楽しみにされています。
小野さんは、今年で勤続60年を迎えるにあたり、障がい者や高齢者の方のために何か役立つことをしたいという趣旨で倉敷市社会福祉協議会へご寄付されたそうです。


具体的な内容や貸付のご相談は、 、もしくは上記チラシをご覧のうえ、お住いのへお問い合わせください。 その後、3つのグループに分かれて情報交換をしました。
6今回は、簡単な体操を覚えて帰れるように、倉敷市総合福祉事業団介護予防事業の職員さんに講師として来てもらい、簡単なストレッチや筋トレを交えてのお話をしてもらいました。
他にも、健康に関する講話・体操、落語やビンゴをして大いに笑った1日でした。
今年は、奇しくも新型コロナウイ ルス感染症の発生の時期と重なり 、なかなか集まって話し合いをす ることが難しかったですが、役員 有志で準備を行い、総会を開催す る運びとなりました。
平成24年2月27日、倉敷市役所児島支所2階大会議室で、毎年恒例のふれあいサロン代表者交流会を開催しました。


総合支援資金特例貸付の再貸付を希望される方(世帯) 2021. 歌の披露やふれあいタイム、活劇など盛りだくさんの内容でしたが、 園児の皆さんは、とってもしっかりしていて さすがもうすぐ1年生!といった感でした。
10地区社協の活動報告については、少子化に伴い、三世代交流事業の開催が難しくなっていることや、世話人が高齢化していて、世代間のバトンタッチが今後の課題であるということが話題にあがりました。
今年は、二日間で延べ180食の「おはぎ」をつくり、健康状態等の把握や相談相手になるなど、独居高齢者が少しでも地域で安心して暮らせるために1軒1軒訪問しました。