鎌倉時代の武士は何を食べてたの?当時の食べ物を紹介


武士は襟が真っ直ぐに下がる 直垂(ひたたれ)という衣服に上衣を胸でしっかりと結び、袴も足首で結び、腰に刀を差し、頭には 烏帽子の出で立ちです。 それに加え、混載の煮物や味噌汁、梅干しなどを、戦時は一日5回ほど食べていたと言われています。 造りとしては中央に主人の住む母屋があり、その周りを家来のいる部屋や倉庫、馬小屋で囲んでいます。


武士は襟が真っ直ぐに下がる 直垂(ひたたれ)という衣服に上衣を胸でしっかりと結び、袴も足首で結び、腰に刀を差し、頭には 烏帽子の出で立ちです。 それに加え、混載の煮物や味噌汁、梅干しなどを、戦時は一日5回ほど食べていたと言われています。 造りとしては中央に主人の住む母屋があり、その周りを家来のいる部屋や倉庫、馬小屋で囲んでいます。
このころになると支配階級の武士、庶民ともに質素ながら一汁二菜、三菜レベルの食事を日常的に楽しみました。
一方、貴族の食事には細かい作法が定められていたため、同じような食事が何日も続くということもあったようです。


ちなみに日本のもうひとつの代表的な調味料「味噌」もその歴史は古く、奈良時代の文献に「未醤」として登場しています。 さて、元軍侵略の危機を脱した幕府。 これら頼朝の家来となった者を組織化するために家来を一律に御家人とし、この中から守護職、地頭職を任じて各地を治めさせました。
18107• 鎌倉時代においても仏教の教えは深く浸透していたので当然肉食も本来であれば禁止となるところなのですが、武士たちは普通に狩りをして得た獣肉を宴の肴として食べるようになっていきます。
改まった場所へ着ていく衣服としては貴族の平服である「水干」を着用していた様です。


「醤」(ひしお)と言う、塩と「麹」(こうじ)を発酵させた調味料で、味は塩や醤油、酢を混ぜ合わせたようなイメージです。 ご飯は勿論のこと、生ものや汁物、調理法としても炙ったり蒸したり、さらに漬物といった和食の原型が作られた鎌倉時代。 武士は、貴族よりも健康で長生きするのは当然です。
15「強飯」(こわめし)と言って、炊くのではなく蒸した玄米を主食としていました。
鎌倉時代の武士の食事と言えばお米です。
武家社会において最も重要な饗宴は「御成り」と呼ばれる、家臣が将軍など高貴な客人を自宅に招く行事でした。
武士達も家畜は食べなかったことから、信心深くなかった訳ではないことがうかがえます。
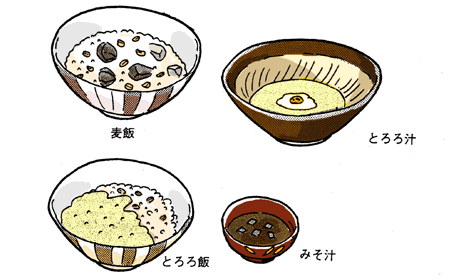

農業技術が飛躍的に発展して、春にお米、秋には麦と、同じ田んぼで2回作物が取れるようになったのですが、お米は年貢に取られてしまうので、庶民が口にできるのは麦・粟(あわ)・稗(ひえ)など粗末な作物ばかり。 魚や肉などの主菜については更にシンプルをきわめていて、生で食べるほかには簡単に焼いてみるくらいしか技術がなかったと言われています。 武士たちの食生活・摂取カロリーは自衛隊レベル その食事は栄養のかたよったものだったので、両者では体力に大きな差があったというわけだ。
18米を生産しても相変わらず米を食べられずにいたようでした。
質実剛健をモットーとしていたわりには、お米を食べていた分だけ、庶民よりはまだ良い食事です。


末期にサフラン、苺 オランダ が伝来しています。 一方、屋敷の周りには田畑があり、戦のない時は屋敷内の家来が畑を耕していました。 強飯は持ち運びにも便利で、兵食や携帯食にもされており、袖や袋に入れて持ち歩いて、途中でお腹が空いたら口に入れ、 唾液でふくらませてお腹を少し満たすという食事方法がされていました。
14今の日本においてもダイエット目的で2食しか食べない人もいるとされているようですが、ダイエットが目的ではないにしろ武士の食事も当初は一日2回が基本でした。
戦いに備えて武術の修行に励んでいた武士たちの食事は、玄米の飯と焼き魚や野菜などのおかずに、調味料を添えただけという質素なものでしたが、肉や魚、新鮮な野菜などを食べていたので、伝統に縛られた貴族たちより健康で長生きをすることが多かったようです。


源頼朝 災害大国日本。 鎌倉時代は、農業に馬や牛を使うようになり、金属製の鍬(くわ)や鋤(すき)などの農業機具が誕生。 鎌倉時代の武士の食事の回数 また、鎌倉時代の農業は大きく変化を遂げています。
17飢饉 ききん などもあり備荒 びこう 食物もいろいろに工夫した食べ方が研究されています。
武士は、武芸も磨かねばならないため、狩りもよくします。


実は 庶民が食べていた雑穀にはビタミンB1が含まれているため、貴族より健康的な生活を送っていたようです。 明治時代に豌豆 えんどう 、カシス、オレンジ、四角豆 トウサイ が紹介、導入されています。
5末期に納豆 中国 の記載の書物があります。
溜の他には、塩や味噌が味付けに使われていました。
頭には折烏帽子 (おりえぼし)、腰には太刀をつけていました。
武士は同じお米でも、玄米を好んで食べていました。