私が選んだ心に残る詩歌

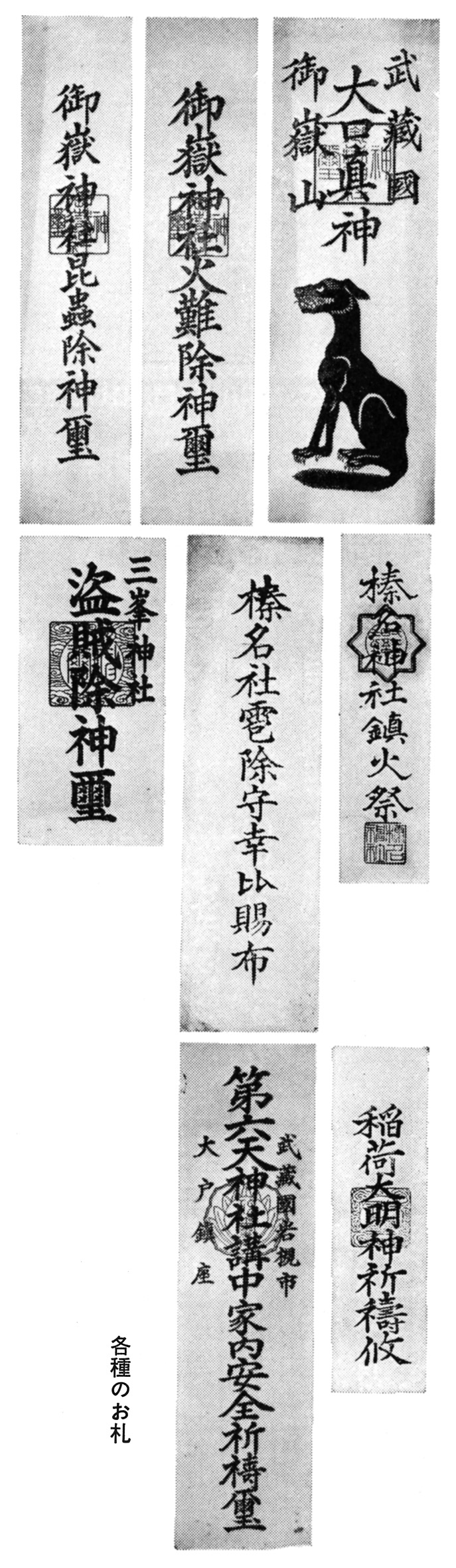
春には雪が溶けて若葉が萌える。
9この歌はそれを示している。
13掲載) 顔ありき咲きかけの梅林に入る 岡井省二 [句集『明野』(1976年)] 捨菜の花墓群見ゆるばかりなり 石田波郷 [句集『春嵐』(1957年)] 春の雲また石庭の上に来ぬ 星野麥丘人 [句集『寒食』(1983年)] 白梅のもっとも近きところまで 漠 夢道 [句集『くちびる』(2002年)] 春禽のすこし汚れて橋の上 藺草慶子 [句集『野の琴』(1996年)] 風といふきれいな味方春の服 恩田侑布子 [句集『空塵秘抄』(2008年)] 人の死に馴れてもの食ふ花の昼 岸田稚魚 [句集『紅葉山』(1989年)] むらさきの貝が口開く春の雨 小島 健 [句集『蛍光』(2008年)] 春の旅くれなゐの陽を沈めたる 森 澄雄 [句集『鯉素』(1977年)] 空浅きところに月や種下し 小林貴子 [句集『紅娘』(2008年)] 花粉症の症状が出るようになって十数年になります。


今日鬢絲 禪榻 畔, 茶煙 輕颺落花風。 名前としてふさわしくないとお考えの場合は、その理由と、 改善案をご提示いただければ幸いです。 わかってはいるが,その死が来るのは突然である。
5根拠もなく推し量って。
もとは「うつしおみ」が「うつそみ」を経て音変化した言葉で、この世に生きている人の意。

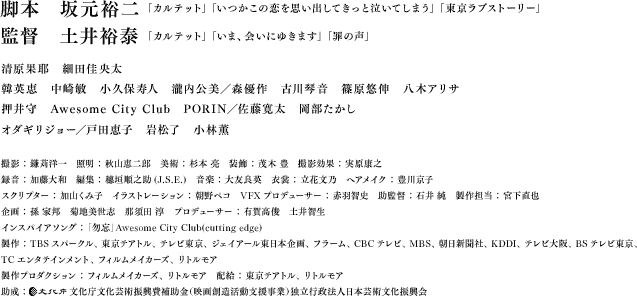
号して醉翁、六一居士。 李淸照は、この作品に感動し、「庭院深深深幾許」で始まる「臨江仙」(「蝶戀花」ではなく)を何 か作っている。
疑問詞「いづち」を受けて場所を推量する用法。
六花は、結晶が六角形であるところから。
友だちの久しうまうでこざりけるもとに、よみてつかはしける 水のおもにおふる五月の浮き草の憂きことあれやねをたえてこぬ (古今976) 【通釈】水面に生えている五月の浮草ではないが、憂きことがあるのだろうか、まるで浮草の根が切れたようにぷっつりとあなたの音信も絶えた。
(写真はウィキペディアより) 気になったことば ・偶坐(ぐうざ):「向かいあって座る」の意。

— 嘯月庵 shogetsuan 本記事では、 「願わくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
そこから「暢気」「呑気」などの字が当てられたそうです。
「ばや」は接続助詞「ば」と疑問の助詞「や」。
新しい主のもとで、ひな人形を飾って華やいでいます。
作者に思いを馳せ、詠まれた背景を想像しながら、俳句を通して春の季節を楽しんでみるのもいいかもしれません。
享年37歳。
医療の発達していない当時はなおさらだったことだろう。


23歳で出家して円位を名乗り、後に西行とも称しました。 (西行法師 出典:Wikipedia) この歌の出典は 『山家集』。 10句のなかに「正直に腹減つてくる梅の花」「古墳より少年が来る花の昼」「一握の落花湯船に放ちけり」などが同時にあるのが落ち着かないようにも思うのですが、花の咲く前の、そんな時間らしい選になっているのかもしれません。
24掲載) 男らの出ては汚しぬ春の雪 星野麥丘人 [句集『弟子』(1976年)] ポリバケツにホースの先と桃の花 対中いずみ [「椋」第34号(2010年6月)] 空高く晴れたる田打桜かな 茨木和生 [句集『山椒魚』(2010年)] 山雲のくぢらのごとき利休の忌 和田耕三郎 [「OPUS」第22号(2010年5月)] 入学の子のなにもかも釘に吊る 森賀まり [句集『ねむる手』(1996年)] 一村の家がよく見え李咲く 森 澄雄 [句集『鯉素』(1977年)] ぶらんこの鎖に星の匂ひかな 山西雅子 [句集『沙鴎』(2009年)] 鈴の音のやうな耳鳴り春落葉 中岡毅雄 [句集『啓示』(2009年)] 囀りて鳥は命を軽くせり 小林貴子 [句集『紅娘』(2008年)] この町のふところ深き暮春かな 石田郷子 [句集『秋の顔』(1996年)] 横浜は、まもなく梅雨を迎えようとしています。
勅撰入集二百十四首。
幼な子の髫 うない の垂れ髪が乱れているように降る五月雨の空に。
それを目に当てて透かすようにしてみていくと、その色の美しさは一層増し、それからだんだんとピンク色は薄くなり、むこうの青々とした海が透けて見えてくるように思えてきました。